![]()
2015年11月5日 No.906
![プリントする]()
![他のホリデーを読む]()
無言の証人
アウシュヴィッツを征く 後編
人類が二度と繰り返してはならない『負の遺産』として
後世の人々にホロコースト(大量虐殺)の歴史を
伝え続けるアウシュヴィッツ元収容所。
ポーランドの緑豊かな田園地帯で今も異彩を放つ
この収容所跡について、
前編から引き続きお送りすることにしたい。
●サバイバー●取材・執筆・写真/ 本誌編集部
※本特集は、週刊ジャーニー2004年12月2日号に掲載したものを再編集し、2回に分けてお届けしています。
![auschwiz2]()
▲アウシュヴィッツに保管されている、おびただしい数の靴。持ち主がどのような運命をたどったかは、改めて言うまでもないだろう。
Special Thanks To:
Polish National Tourist Office, Level 3, Westgate House, West Gate, London W5 1YY
Tel: 0300 303 1812
E-mail: london@poland.travel
Homepage: www.poland.travel/en-gb
Polish National Tourist Office in Krakow
Homepage: www.krakow-info.com
参考文献:『ユダヤ人』上田和夫著(講談社刊)/『ヒトラーとユダヤ人 悲劇の起源をめぐって』フィリップ・ビューラン著、佐川和茂・佐川愛子訳(三交社刊)/『ホロコーストを学びたい人のために』ヴォルフガング・ベンツ著、中村浩平・中村仁訳(柏書房刊)、このほか関連ホームページ各種
強制移住計画の挫折の果て
ホロコーストの代名詞であり、「死のキャンプ」「死の大量生産工場」として稼動することになるアウシュヴィッツの建設が始まったのは1940年。
「前編」では、極貧生活の中でヒトラーがユダヤ人に対して抱くようになった異常なまでに激しい憎悪、そして偏見に満ちた主張などが、いかにしてこのアウシュヴィッツに代表される「収容所」へとつながっていったかについて触れた。不条理きわまりない主張の数々が、一国の指導者、しかも独裁的立場にある人物から発せられたことは、恐ろしい限りである。
ただ、ヒトラーは政権に就いた時(33年)から、ホロコーストを計画していたわけではないという見方がある。ユダヤ人をドイツのみならず、各国から追放し、どこかに監視つきの専用居住地を定め、そこにおしこめることを一時は真剣に考え、マダガスカル島(英国との関係悪化で挫折)や、ロシア(第二次世界大戦での対ロシア戦の長期化により挫折)の一部などが候補にあがっていたという。
ゲットー(ユダヤ人居住区)を定め、財産を没収し、教職をはじめとする公職につくのを禁止することにより、当初は、ユダヤ人勢力封じ込めの目的は達成されていた。
しかし、第二次世界大戦の戦況が思わしくなくなるにつれ、ヒトラーおよびナチス上層部の態度は過激さを増していく。おそらく41年ごろ、ユダヤ人問題の「最終解決=絶滅」という図式が成立し、国家を挙げてその実現に突き進んだとする解釈は説得力のあるものと思える。
![]()
収容棟のまわりには、高圧電流の流れた有刺鉄線が
張り巡らされていた。アウシュヴィッツにて。
こうして「絶滅収容所」での「最終解決」策が『効率的』に実行されるに至る。アウシュヴィッツはその実践地の中でも、特筆に値する存在だった。ちなみに、もとの地名はオシフィエンチムだったが、その前年、ポーランドがドイツ軍との戦闘に破れ、ドイツ第三帝国の一部に組み込まれたため、アウシュヴィッツのドイツ名が与えられていたのだ。
戦前、ポーランド軍の施設があったアウシュヴィッツに収容所建設地の白羽の矢がたったのは、交通(鉄道)の便がよく、それでいて適度に人口密集地から離れていたためとされる。
ゲットーは、はずれとはいえ市街地に接していることが多かったため、ゲットーと外の世界のつながりを完全に絶つことは難しく、情報交換、援助などが続けられがちで、「絶滅収容所」として使用するには適さなかった。また、ナチスは「絶滅収容所」で何が起こっているかを知られたくなかったのである。
当時、ヨーロッパを中心に1100万人のユダヤ人がいたと推定されているが、ホロコーストにより約600万人が犠牲となり、そのうちの150万人がアウシュヴィッツで灰と化したとされている。これらについてもナチスが意図的に証拠隠滅を図ったため、はっきりした数字を確認するすべはない。しかし、総数が500万、あるいは400万だったからといって、ホロコーストが起こったという事実の重みが減じられるものではない。この点を論争の焦点にすること事態、無意味というべきだろう。
働いても待つのは死のみ
「労働が自由をもたらす(Arbeit macht Frei)」―アウシュヴィッツへの入り口だけでなく、ほかの複数の収容所にも掲げられていたモットーだが、ナチスによる悪質な意地悪、皮肉、あるいは欺きとしかとりようがない。
ここアウシュヴィッツでは、150万人が働いても自由になれなかったばかりか、生きることさえ許されなかったのだ。
収容所の設立命令が下ったのが1940年4月。所長には、戦後、絞首刑に処されることになる、悪名高いルドルフ・ヘスが任命され、同6月14日には、700人余りのポーランド人が政治犯として収容された。
以来、平均収容者数は1万3000―1万6000を推移。多い時には2万8000人が一度に収容されたこともあったようだが、すぐに人数は「調整」された。通常よりガス室を頻繁に使えば済むことだったろう。
![]()
アウシュヴィッツの焼却炉。いったんナチスに
爆破されたが、復元されたもの。
さて、このアウシュヴィッツ収容所跡こと、「国立オシフィエンチム博物館」へは、クラクフを拠点に日帰りで訪れるのが一般的。第二アウシュヴィッツの別名を持つ、ビルケナウ収容所とあわせて、両方を見学するツアーを利用するのが便利だ。ただ、季節により、また使用するツアー会社により、1グループあたりの人数は大きく違う。大型バス1台分で1グループというような場合は、ガイドの説明を聞くのも一苦労。できれば、ミニバスツアーで、1グループ10人以下程度のものを探して参加したい(ツアー会社によっては、日本人ガイドを頼むことも可能)。
我々取材班が参加したツアーは、午前9時半にクラクフを出発した。アウシュヴィッツまでは一車線道路。クラクフ郊外の田園地帯を安全運転で走ること1時間余り、11時前に現地に到着した。
11時から20分間、ホロコーストに関するショートフィルムを見て下準備をし、それからようやく実際の収容所跡ツアーがスタートした。
銃殺時に使われ、殺される者は壁を向いて立たされたという「死の壁」、集団絞首台、懲罰のための独房、ガス室、そして焼却炉…ガイドの淡々とした説明が逆に恐ろしい光景を思い描かせる。他人に対して、どんなに残酷なことをしても許されるという状況に置かれたら―普通の人々の日常生活で、それは「ありえない」ことだが、70年前、ここではそれが当たり前の現実だったのだ。
どの展示も、ホロコーストの酷さを示し、二度と繰り返さないように「忘れないで」と懸命に訴えているように感じさせたが、最も印象深かったのは、第5棟の「犯罪証拠」と題された展示だった。
![]()
ビルケナウの収容者用トイレ。許された
使用時間は1分だけだったという。
ナチスは、驚くべき律儀さと勤勉さを発揮し、利用できそうなものはすべて集めて保管した。35あった保管倉庫のうち、ナチスに破壊されずに残ったのは6棟のみというが、そこから発見されたものだけでも、思わず絶句する量だった。衣服はいうに及ばず、メガネ、カバン、ブラシ類、洗面器類、流用できるのか疑問に思う義足から、毒ガスとして使われたとされるチクロンBの結晶が入っていた空き缶などまで、何でも保管してあった。その中には約2トンの頭髪も含まれていた。頭髪は1キロあたり半マルクで販売され、ドイツ本国で靴下や毛布用の職布として利用されたという。
この頭髪もショッキングだったが、筆者が最も胸をしめつけられたのは、靴の山だった。展示室の両脇に積み上げられた靴、靴、靴、靴…。夏に収容された者がはいていたと一目でわかるサンダル、冬のブーツ、女性の赤いパンプス、子供の小さな靴。衣服や頭髪以上に、その持ち主の運命を雄弁に物語っているように感じられて立ちすくんでしまったのだった。
![]()
上の地図は、1942年、第3帝国時代のドイツ(大ドイツ国)の領土を示すもの。
Martin Gilbert: The Holocaust: The Jewish Tragedy, London 1986より
*赤い点線は1942年末のドイツ軍前線、
![収容所]()
は主な収容所のあった場所
「死の門」をくぐった線路
約2時間のアウシュヴィッツでの見学を終え、今度はビルケナウ(ブジェジンカ)へ。8キロしか離れておらず、車で10分弱の場所だ。
1945年1月27日、アウシュヴィッツとともに、ソ連軍により解放されたこのビルケナウは、証拠隠滅をあせるナチスにより大幅に破壊され、アウシュヴィッツほど「展示物」が残されていない。しかし、鉄条網に囲まれた敷地はアウシュヴィッツよりはるかに広大で、また、わずかに残る収容棟が粗末な木造バラックであるため、アウシュヴィッツより、さらに大規模に、ただ「絶滅」のために急いで造られた場所という印象を受けた。
![]()
2003年にフジテレビでリメイクされたドラマ『白い巨塔』で、
主役の財前五郎を演じた唐沢寿明が「死の門」をバックに
立つシーンは印象深かった。
©Fuji Television Network Inc.
このビルケナウで、最もよく知られている写真の構図といえば、線路伝いに、「死の門」と呼ばれたSS中央衛兵所を望むものだろう。テレビのリメイク版『白い巨塔』で、唐沢寿明扮する主役が、ふたまたに分かれた線路の間で立ちつくすシーンにも使われた。
列車でここまで運ばれてきた人々は、SSの医師たちにより選別され、すぐにガス室に送られるか、劣悪な条件のもと、死の恐怖と隣り合わせの中、過酷な重労働に就かされるかのどちらかだったのだ。しかも、重労働の先に待っているのも、やはり死のみ。いかに絶望せずに、行き続けるか。生き残った人々の運と精神力の強さに感嘆するほかない。
ここでの約40分の見学を終え、クラクフの街に戻った取材班は、その夕刻、ワルシャワに移動した。クラクフと首都ワルシャワはポーランドの誇る高速列車で、ノンストップで結ばれている。所要約2時間半の快適な旅だ。車窓には、ポーランドでは農業がまだまだ主要産業のひとつであることをうかがわせる、牧歌的な景観が広がる。
![]()
ビルケナウの「死の門」。収容者を詰めこんだ列車は
この門をくぐり、敷地内に入った。列車が到着するなり、
すぐに『選別』が行われたのだった。
美しいのだが、なぜか切なく哀しいものに映って困った。18世紀末、ロシア、プロイセン、オーストリアの3国によって、3度にわたり分割されたばかりか、20世紀に入ってからは、39年から6年間ドイツ軍に占領され、第二次世界大戦後、名目上は独立したものの、ソ連の強い影響から逃れられず、国として真にひとりだちできるようになったのはソ連崩壊後といえるポーランド。そしてそのポーランドの絶滅収容所で失われた何百万という人命。お世辞にも幸福とはいえない一連の歴史が、風景をも違ったものに見させていたのだろう。やがて、西の空は鮮やかな夕焼け雲に覆われた。日本でも英国でも見ることのできないような、紅い紅い夕焼けだった。
前編に戻る…
![]()
![]()
| ナチス関連年表 |
|---|
| 1914年7月28日 |
第一次世界大戦勃発(オーストリアがセルビアに宣戦布告) |
|---|
| 1918年11月9日 |
ドイツ革命(皇帝ヴィルヘルム2世退位、オランダへ亡命) |
|---|
| 11月11日 |
ドイツが休戦協定に署名。事実上、第一次世界大戦終了。ヒトラーは対英戦での負傷で入院中、この知らせを受けた |
|---|
| 1919年1月5日 |
ナチス結成 |
|---|
| 6月28日 |
ヴェルサイユ条約調印 |
|---|
| 1923年11月8日 |
ヒトラー、ミュンヘン一揆を起こすが失敗(ヒトラー自身を長とする「国民政府」樹立を目指し、ミュンヘンでクーデターを実行。バイエルン州総督らを武力でもって賛同させようとしたが、あっけなく失敗し翌日逮捕され、有罪となり禁固刑を科される) |
|---|
| 1924年12月20日 |
ヒトラー、出獄(獄中、副総統ヘスに口述筆記させ、『我が闘争』〈英語名『My Struggle』〉を完成させる) |
|---|
| 1932年7月31日 |
ナチス、第1政党になる |
|---|
| 1933年1月30日 |
ヒトラー内閣成立(ナチ党員は、首相のヒトラーを含め、3名が閣内入りを果たしたに過ぎなかった。副首相パーペンら保守派はナチスに実権を与える気はなく、ヒトラーを「飼いならす」つもりだったが、まもなくその見立てが甘かったことを知る) |
|---|
| 4月26日 |
ゲーリングを長官とする、ゲシュタポが発足 |
|---|
| 1934年8月19日 |
ヒトラー、首相と大統領を兼任 |
|---|
| 1935年3月16日 |
ヴェルサイユ条約を破棄し、ドイツは再軍備宣言を行う |
|---|
| 9月15日 |
ニュルンベルク法公布(ドイツで、ユダヤ人迫害を合法的に行うことが可能になる) |
|---|
| 10月21日 |
ドイツ、国際連盟脱退 |
|---|
| 1936年8月1日 |
ベルリン・オリンピック開催 |
|---|
| 1937年11月6日 |
日独伊防共協定成立 |
|---|
| 1938年3月13日 |
ドイツ、オーストリアを併合 |
|---|
| 11月9日 |
「水晶の夜」事件(ユダヤ人の店などが各地で襲われ、路上に散乱したガラスの破片が水晶のように光ったことから、こう呼ばれる) |
|---|
| 1939年9月1日 |
第二次世界大戦勃発(ドイツ軍、ポーランドに侵攻開始。翌年4月にはノルウェーに侵攻、デンマークを無血占領) |
|---|
| 1940年5月1日 |
ルドルフ・ヘス、アウシュヴィッツ収容所の所長に任命される |
|---|
| 6月22日 |
フランス、ドイツに降伏(翌年4月、ギリシャがドイツに降伏) |
|---|
| 1941年6月22日 |
ドイツ、ソ連と戦闘開始(モスクワ、スターリングラードを対象に大々的な軍事作戦が繰り広げられたが、43年には、スターリングラードのドイツ軍が降伏) |
|---|
| 1943年9月8日 |
イタリア、無条件降伏 |
|---|
| 1944年6月6日 |
連合軍、ノルマンディ上陸作戦開始 |
|---|
| 7月20日 |
ヒトラー、暗殺計画失敗 |
|---|
| 8月25日 |
連合軍、パリを解放、11月にはソ連軍がドイツ国境内に入る |
|---|
| 1945年4月22日 |
ソ連軍、ベルリン市街に突入 |
|---|
| 4月30日 |
ヒトラー、エヴァ・ブラウンとともにベルリンにて自殺 |
|---|
| 5月7日 |
ドイツ、無条件降伏 |
|---|
トラベルインフォメーション ワルシャワ
※情報は2015年11月2日現在のもの。
![]()
◆ポーランドが初めて統一されたのは10世紀後半のころ。当時の首都はクラクフで、ヨーロッパでも有数の富裕な都市として発達、16世紀にはルネサンス文化が栄えるなどしたが、東のロシア、西のプロイセン(後のドイツの一部)、南のオーストリアと、まわりを強国に囲まれ、常にそれらの脅威にさらされる宿命にあった。この3国により、1772年(第一次)、93年(第二次)、95年(第三次)と三度分割され、95年の分割で、事実上、国としてのポーランドはいったん消滅してしまう。
◆独立運動を続けた結果、1918年、ようやくポーランド共和国として復活。しかし、これも長続きせず、39年、ヒトラー率いるナチス‐ドイツに占領された。ナチスの敗北を受けて、45年6月には統一政府が誕生するも、今度は、ポーランドを解放してくれたはずのソ連の影響下に入り、「東欧」として共産圏の一部に組み込まれた。真の独立は、ソ連崩壊後といっていいだろう。2004年5月にはEU加盟を果たした。
◆このポーランドの首都ワルシャワの歴史は比較的浅い。1596年、ジグムント3世=左上の像=がクラクフよりワルシャワへの遷都を行い、1611年から正式に首都となった。第二次世界大戦時、ドイツ軍の猛攻にあい、街の8割は灰と瓦礫の山と化したが、戦後、絵画や写真などの記録を頼りに「壁のひび」まで忠実に再現すべく、気の遠くなるような復興作業が市民によって行われ、今の町並みが作られたという。
◆ワルシャワには、戦争慰霊碑がいたるところにあるが、不屈のポーランド国民の誇りが結集した街といえるだろう。
◆見どころは、旧市街(一部、市壁が残る市場広場が中心)、およびそこから南にのびるクラクフ郊外通りと、しゃれたカフェやレストランも多い、新世界通り沿い(長さはあわせて約1キロ)に集まっているので、効率よく観光できる。
【時差】 英国より1時間早い
【ビザ】 90日以内の観光なら不要(残存有効期間は91日以上必要)
【通貨】 ズウォティ(Zloty)。補助通貨はグロシュ(Grosz)で、1ズウォティ=100グロシュ。2015年11月2日現在の為替レートは1ズウォティ=約17ペンス
【喫煙事情】 通りのゴミ箱には、必ずといっていいほど灰皿がついているくらい、喫煙には寛容。ただ、ワルシャワ空港内は、完全禁煙(バーでもダメ)なのでご注意!
主要な観光スポット
*オープン時間、入場料、イベントなどについては、ワルシャワの王宮広場にあるツーリスト・インフォメーションセンター、あるいは各スポットのホームページなどでご確認ください。
Tourist Information: Stoleczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej
Plac Zamkowy 1/13, 00-267 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 635 18 81
www.warsawtour.pl
キュリー夫人博物館 Muzeum Marii Sklodowskiej Curie
![]()
© Adrian Grycuk
1903年、放射性元素の発見により、夫とともにノーベル物理学賞を受賞したマリー・キュリー夫人。夫亡き後も研究を続行し、ラジウムの分離に関する発見に対して、1911年にはノーベル化学賞も受賞するという偉業を成し遂げた。日本では教科書によく登場するため馴染み深いこの女性の生家が、博物館として公開されている。
Freta 5
Tel: 22 831 80 92
http://en.muzeum-msc.pl
バルバカン Barbakan
![]()
© Carlos Delgado
ワルシャワ旧市街(Stare Miasto)の中心といえる旧市街市場広場(Rynek Starego Miasta)は市壁に囲まれていた。その壁の内側に入るための玄関口といえるのがバルバカン。英語でいう「バービカン(Barbican)」(=楼門、物見やぐら)と同じで、砦、あるいは牢獄として使われていたもの。戦火の被害にあったが、見事に復元されている。
ul. Nowomiejska
Tel: 22 531 38 02
http://muzeumwarszawy.pl/muzeum/lokalizacje/barbakan
ワルシャワ歴史博物館 Muzeum Historyczne Miasta Stolecznego Warszawy
ワルシャワ復興に関する展示が充実。
Rynek Starego Miasta 28
Tel: 22 635 16 25
www.stare-miasto.com/muzeum_historyczne.html
旧王宮 Zamek Krolewski
![]()
© Alina Zienowicz Ala z
首都をクラクフからワルシャワに移したジグムント3世の像を頂く石柱が中央にそびえる、王宮広場に面して建つ。かつてはジグムント3世の居城だった。内部は美術品など展示をする部分と、復元された「王の部屋」をはじめとする各部屋を公開する部分に分かれている。日曜日には一部の見学ルートが無料になるため、長い列ができる。
plac Zamkowy 4
Tel: 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl
聖十字架教会 Kosciol sw Krzyza
![]()
コペルニクス像の向かいに建っている教会。中に入ると、大きな柱がいくつか目に入るが、向かって左側手前にある柱の下には、20歳で政情不安定なポーランドを離れてから、一度も祖国の土を踏むことなく39年の生涯を終えた、ショパンの心臓が埋葬されている。第二次世界大戦時、ドイツ軍に爆破され大きな被害を被ったばかりでなく、心臓も持ち出されてしまったものの、戦後の1945年10月17日、ショパンの命日に元に戻された。
Krakowskie Przedmiescie 3
Tel: 22 826 89 10
www.swkrzyz.pl
コペルニクス像 Pomnik M Kopernica
![]()
地動説を唱えたことで知られる、ミコワイ・コペルニクス(Mikolaj Kopernik 1473~1543)はワルシャワから180キロ ほども離れたところにある、トルンという町の出身。ポーランドを代表する偉人のひとり。
ショパン博物館 Muzeum Fryderyka Chopina
![]()
科学だけでなく、芸術面でもポーランド人が優れていることを証明した、フレデリック・ショパン(Fryderyk Chopin 1810~49)。自らも秀でたピアノ奏者だったショパンは、数々の名曲を残した。この博物館には、ショパンが最後に使ったといわれているピアノから、直筆の譜面、手紙まで、ショパンに関する2500点以上の資料がおさめられている。また、3階はコンサートホールとしても利用されている。
Okólnik 1
Tel: 22 441 62 51
http://chopin.museum/pl
文化科学宮殿 Palac Kultury i Nauki
![]()
ワルシャワ中央駅のすぐ近くにあり、37階建て、高さ234メートルという高層ビルなのでよく目立つ。「宮殿」というよりは、「博物館」兼「一大イベント会場」ともいうべき建物で、展望台もある。中には科学技術博物館、プラネタリウム、進化博物館(恐竜の展示などもあり)のほか、ポーランドTV、コンサートホールや映画館、劇場も入っている。スターリンからの「贈り物」として、1952年から56年にかけて建造されたが、ポーランド市民からすると「おしつけられた」という意識が強いらしく、「贈り物」とは名ばかりで、ポーランド市民からの税金で作られたと信じている人が少なくないそうだ。「ソ連の建てた、ワルシャワの『墓石』」といった、ありがたくないニックネームもあるという。
plac Defilad 1
Tel: 22 656 76 00
www.pkin.pl
トラベルインフォメーション クラクフ
※情報は2015年11月2日現在のもの。
◆1596年、ジグムント3世がワルシャワに都を移すまで、ポーランドの首都として栄え、それ以降も輝きを失うことなく、現在は古都として愛されている都市、クラクフ。ナチスードイツ占領下でも、司令部がここに置かれたため戦火をのがれたといい、美しい町並みが保たれている。
◆ワルシャワ以上に見どころが多いといってよく、市壁に囲まれた旧市街(Stare Miasto)はコンパクトにまとまっており、そぞろ歩きを楽しみながら観光したい場所だ。バルバカンから中央市場広場へ抜け、この広場から城へと向かえば、主要な観光ポイントをおのずと訪れることになる。
◆なお、旧市街を出て、南に下ったところにあるカジミエーシュ地区(Kazimierz)は、戦前、ユダヤ人が多く住んでいたところだった。14世紀なかばにヨーロッパを襲ったペスト(黒死病)により、ユダヤ人はその災禍の原因であるとして迫害され、多くのユダヤ人が、中欧、さらには東欧へと逃れた。農業国ポーランドは、商業・工業面で立ち遅れており、支配者層はユダヤ人の流入をむしろ歓迎したため、特に多くのユダヤ人が移り住んだ。カシミール(カジミエーシュ)3世(1310~70)などは、ユダヤ人を厚遇したことで知られるが、ユダヤ人は手工業の知識、商業のノウハウをいかして期待にこたえ、ポーランドの発展に尽力したのだった。
◆ヒトラーが、ユダヤ人絶滅収容所をポーランドに作ったのは、同国が多くのユダヤ人を抱えていたことと密接に関係している。
◆映画『シンドラーのリスト』にもでてきた、クラクフのユダヤ人コミュニティは壊滅的な打撃を受けたが、もとの彼らの居住区、カジミエーシュ地区は、現在はしゃれたバーやレストランが集まるトレンディなエリアとして注目されている。
【ワルシャワからのアクセス】
*アウシュヴィッツ収容所だけが目的の場合はクラクフ空港に入るのがベストだが、ワルシャワでの観光も含めたい場合、空路ワルシャワに入り、ワルシャワ~クラクフ間は電車で移動するのが一般的。ワルシャワ~クラクフ間は、ノンストップで約2.5時間。
![]()
ポーランドでぜひお試しいただきたいのが、水ギョウザそっくりの「ピエロギ(Pierogi)。ひき肉、チーズ、野菜(キャベツの酢漬けが一般的)など、具はいろいろ。ただし、皮がかなり厚いため、すぐにおなかいっぱいになるのでご注意を。
主要な観光スポット
![]()
*オープン時間、入場料、イベントなどについては、ツーリスト・インフォメーションセンター、あるいは各スポットのホームページなどでご確認ください。
Tourist Information:
Punkt Informacji Miejskiej
ul. Szpitalna 25 Kraków, Poland
Tel: +48 12 432 00 60
www.krakow.pl
バルバカン Barbakan
![]()
旧市街を囲む市壁内に入るための玄関口である、楼門。騎士たちの多くは右利きで、盾は左手、剣は右手に持つのが普通だったので、ここに入る際、騎士たちは盾で覆ってない、体の右半分をフロリアンスカ門の衛兵(いつでも矢を放てるように構えていた)に見せて入場するよう、入り口の角度が設定してあったという。
Basztowa
Tel: 12 422 98 77
www.mhk.pl/oddzialy/barbakan
フロリアンスカ門 Brama Florianska
![]()
聖マリア教会 Bazylika Mariacka
![]()
クラクフに数ある教会の中でも、ひときわ目立つ荘厳な教会。1222年建造で、中央市場広場に面してそびえる。昔々、モンゴル軍がクラクフに攻め入ろうとした時、敵が来たことを知らせるために、ある兵士がこの教会の塔の上でラッパを吹き鳴らした。このラッパ手は、まもなくモンゴル兵の放った矢に貫かれて絶命するが、そのラッパ手の死を悼んで、今でも1時間ごとにラッパが吹き鳴らされる。
plac Mariacki 5
Tel: 12 422 05 21
www.mariacki.com
織物会館 Sukiennice
![]()
旧市街の中心である中央市場広場のほぼ中央にある、ルネッサンス様式の建物。14世紀に建造され、当初は衣服や布地の取引所として使われたため、この名がついた。中には土産物屋がぎっしりとならび、華やかな雰囲気が漂う(ただし、値段は少々高め)。2階は国立美術館(Galeria w Sukiennicach)。また、中央市場広場のまわりにはレストラン、カフェ、店などが軒をならべ、いつもにぎわっている。
Rynek Główny 1-3
Tel: 12 433 54 00
http://mnk.pl/oddzial/galeria-sztuki-polskiej
聖ペテロ・聖パウロ教会 Kosciol sw Piotra I Pawla
![]()
教会の外に聖人たちがずらりと並んでいるのは、中が小さすぎるため、というジョークがささやかれる教会だが、実際にはかなり大きく、かつ荘厳。
Grodzka
www.apostolowie.pl
ヴァヴェル城 Zamek Krolewski na Wawelu
![]()
歴代ポーランド王の居城として使われた場所。旧王宮部分にある、王宮博物館(Komnaty Krolewskie)、18世紀まで代々、ポーランド王の戴冠式が行われた大聖堂(Katedra Wawelska)、金色のドームが目印のジグムント・チャペル(Kaplica Zygmuntowska)、ポーランド最大の鐘がつるされているジグムント塔(Wieza Zygmuntowska)など、見どころが多い。なお、このジグムント塔の鐘は、宗教上、あるいは国政上、重要なことが起こった時にしか鳴らされないことになっている。
Wawel 5
Tel: 12 422 51 55
www.wawel.krakow.pl
竜の洞窟と竜の像 Smocza Jama
その昔、ヴィスワ川には竜が棲み着いており、近隣の村の若い娘を食べるとして、憎まれおそれられていた。ある時、靴職人の弟子が、タールと硫黄を毛にしみこませた羊を娘と偽って、この竜に食べさせたところ、のどが猛烈に渇いた竜はヴィスワ川の水をおびただしい量飲み、ついには破裂して死んでしまった、という伝説が残っているという。この靴職人の弟子は、お姫様と結婚し、めでたしめでたし、という結末だが、竜が棲んでいたという洞窟が残っており見学することができる。また、近くに竜の像もあり。
Wawel
www.sktj.pl/epimenides/jura/smocza_p.html
日本美術・技術センター(『マンガ館』) Manggha: Centrum Sztuki i Techniki Japonskiej
![]()
© Zygmunt Put Zetpe0202
日本美術のコレクターだった、フェリクス・マンガ・ヤシェンスキ氏のコレクションを展示。2000点を超える、安藤広重の作品を含む、4600点以上の浮世絵が中心というコレクションのほか、日本文化に関連したものがおさめられている。なお、『マンガ』は、同氏が好んで使ったペンネームで「北斎漫画」からきているそうだが、このセンターにコミックとしての「マンガ」があるわけではない。
Marii
Konopnickiej 26
Tel: 12 267 27 03
http://manggha.pl









 NHS(英国国民医療制度)の臓器提供ウェブサイト(NHS Organ Donation)から、臓器提供の意思の有無を数分で登録できる。最初の画面で「臓器提供に同意」を選択すると、名前や住所といった個人情報の登録画面に進む。ここでは、「すべての臓器を提供する」、または「臓器の一部を提供する」のどちらかが選択できる(臓器の一部の提供を希望する場合、選択肢は、腎臓、心臓、肝臓、小腸、角膜、肺、膵臓、組織の8項目)。登録完了後、登録カード(NHS Organ Donor Card)が郵送されるが、自分でダウンロードすることも可能だ。臓器提供を拒否したい人も、その意思を登録することができる。
NHS(英国国民医療制度)の臓器提供ウェブサイト(NHS Organ Donation)から、臓器提供の意思の有無を数分で登録できる。最初の画面で「臓器提供に同意」を選択すると、名前や住所といった個人情報の登録画面に進む。ここでは、「すべての臓器を提供する」、または「臓器の一部を提供する」のどちらかが選択できる(臓器の一部の提供を希望する場合、選択肢は、腎臓、心臓、肝臓、小腸、角膜、肺、膵臓、組織の8項目)。登録完了後、登録カード(NHS Organ Donor Card)が郵送されるが、自分でダウンロードすることも可能だ。臓器提供を拒否したい人も、その意思を登録することができる。























 【ヴィクトリア女王】ヴィクトリア女王も、犬を飼ったり、乗馬を楽しんだりするなど、動物嫌いではなかった(絵画は、ヴィクトリア女王が14歳の時のもの。足元では、愛犬のスパニエル「Dash」がたわむれている)。
【ヴィクトリア女王】ヴィクトリア女王も、犬を飼ったり、乗馬を楽しんだりするなど、動物嫌いではなかった(絵画は、ヴィクトリア女王が14歳の時のもの。足元では、愛犬のスパニエル「Dash」がたわむれている)。

 【ヴィクトリア女王】ヴィクトリア女王の絵を描く才能はずば抜けていた。自画像、子供たちの姿などを描いているが、その腕前にはうなってしまう(絵画は、ヴィクトリア女王が16歳の時に描いた自画像)。
【ヴィクトリア女王】ヴィクトリア女王の絵を描く才能はずば抜けていた。自画像、子供たちの姿などを描いているが、その腕前にはうなってしまう(絵画は、ヴィクトリア女王が16歳の時に描いた自画像)。
 (2010/118分)
(2010/118分) (2006/104分)
(2006/104分) (2009/102分)
(2009/102分) (1997/106分)
(1997/106分)


 リチャードの逸話の中でもっとも悪印象を与えるのが、ロンドン塔に幽閉された2人の甥殺し。だが2人は実は生きており、ヘンリー・テューダーに殺され、リチャードは罪を被せられたとする説もある。王位継承を正当化したいヘンリーにとって、2人の少年の存在はリチャード以上に脅威になりかねなかったからだ。
リチャードの逸話の中でもっとも悪印象を与えるのが、ロンドン塔に幽閉された2人の甥殺し。だが2人は実は生きており、ヘンリー・テューダーに殺され、リチャードは罪を被せられたとする説もある。王位継承を正当化したいヘンリーにとって、2人の少年の存在はリチャード以上に脅威になりかねなかったからだ。


 「よし! これで挟み撃ちにできる」
「よし! これで挟み撃ちにできる」
 レスター滞在時はいつもレスター城に泊まっていたリチャードだが、なぜか出陣前の1485年8月20日は、当時のタウンホール「Blue Boar Inn」に宿泊した(図右)。城は改装中だったといわれているが定かではない。
レスター滞在時はいつもレスター城に泊まっていたリチャードだが、なぜか出陣前の1485年8月20日は、当時のタウンホール「Blue Boar Inn」に宿泊した(図右)。城は改装中だったといわれているが定かではない。
 リチャードの墓の探索はこれまでも試みられてきたものの、手がかりを掴めたことはなかった。ラングリー氏は当時の地理を徹底的に検証し、現在は駐車場となっている旧小学校の裏地が、リチャードが埋葬されたというグレイフライヤーズ修道院の跡地ではないかと推測。自身が結成したリチャードの名誉挽回に励む「リチャード3世協会」のメンバーに寄付を呼びかけ、発掘資金を集めた。そして再三にわたる説得の末にレスター大学考古学部の協力を得て、発掘作業がスタートすることになる。2012年8月25日、リチャードが埋葬された日からちょうど527年を迎えた日であった。
リチャードの墓の探索はこれまでも試みられてきたものの、手がかりを掴めたことはなかった。ラングリー氏は当時の地理を徹底的に検証し、現在は駐車場となっている旧小学校の裏地が、リチャードが埋葬されたというグレイフライヤーズ修道院の跡地ではないかと推測。自身が結成したリチャードの名誉挽回に励む「リチャード3世協会」のメンバーに寄付を呼びかけ、発掘資金を集めた。そして再三にわたる説得の末にレスター大学考古学部の協力を得て、発掘作業がスタートすることになる。2012年8月25日、リチャードが埋葬された日からちょうど527年を迎えた日であった。

 リチャードが再埋葬された大聖堂。「セント・マーティン教会」として、10世紀にノルマン人により建立。19世紀後半と1926年に改築が行われ、1927年に「レスター大聖堂」と改名された。内陣の床にリチャードを悼む石碑があったが(② ビジター・センターに展示)、これを撤去してリチャードの棺が納められ、その上に石棺が据えられている。入場無料。
リチャードが再埋葬された大聖堂。「セント・マーティン教会」として、10世紀にノルマン人により建立。19世紀後半と1926年に改築が行われ、1927年に「レスター大聖堂」と改名された。内陣の床にリチャードを悼む石碑があったが(② ビジター・センターに展示)、これを撤去してリチャードの棺が納められ、その上に石棺が据えられている。入場無料。
 グレイフライヤーズ修道院跡地の一部で、リチャードの遺骨が発見された市営駐車場の隣にあった廃校を改装した資料館。2014年7月のオープン時には、長蛇の列ができた。リチャードの生涯や遺骨の発掘過程をたどることができるほか、3Dスキャンした遺骨のレプリカ(写真上の中央)、頭がい骨から復元されたリチャードの顔(同上の右端)などを展示している。遺骨の発見場所もガラス越しに見学できる。カフェあり。
グレイフライヤーズ修道院跡地の一部で、リチャードの遺骨が発見された市営駐車場の隣にあった廃校を改装した資料館。2014年7月のオープン時には、長蛇の列ができた。リチャードの生涯や遺骨の発掘過程をたどることができるほか、3Dスキャンした遺骨のレプリカ(写真上の中央)、頭がい骨から復元されたリチャードの顔(同上の右端)などを展示している。遺骨の発見場所もガラス越しに見学できる。カフェあり。 1980年に「リチャード3世協会」が建造。以前はレスター城跡のキャッスル・パークに建っていたが、リチャードの再埋葬を機に、大聖堂前の庭園に移動となった。完成当時は右手に長剣を持っていたものの、2度の盗難に遭い、短めの剣に変えられた。週末のみ開催のウォーキング・ツアー(14時~、2時間、£5)の集合場所はここ。
1980年に「リチャード3世協会」が建造。以前はレスター城跡のキャッスル・パークに建っていたが、リチャードの再埋葬を機に、大聖堂前の庭園に移動となった。完成当時は右手に長剣を持っていたものの、2度の盗難に遭い、短めの剣に変えられた。週末のみ開催のウォーキング・ツアー(14時~、2時間、£5)の集合場所はここ。 1390年に建てられた商業組合の会議所。16世紀にはタウンホールとなり、レスター市長が使用した。2013年にグレートホールでレスター大学による記者会見が開かれ、発掘された遺骨がリチャードと発表された。その後に開催された特別展には、約20万人が訪れた。
1390年に建てられた商業組合の会議所。16世紀にはタウンホールとなり、レスター市長が使用した。2013年にグレートホールでレスター大学による記者会見が開かれ、発掘された遺骨がリチャードと発表された。その後に開催された特別展には、約20万人が訪れた。 リチャードが最後に宿泊した、当時のタウンホール跡地。本来は「White Boar Inn」という名だったが、ボスワースの戦いの後、リチャードの記章「White Boar(白イノシシ)」からオックスフォード伯の記章を用いた「Blue Boar」に変更された。現在はホテル・チェーン「トラベロッジ」が建っている。
リチャードが最後に宿泊した、当時のタウンホール跡地。本来は「White Boar Inn」という名だったが、ボスワースの戦いの後、リチャードの記章「White Boar(白イノシシ)」からオックスフォード伯の記章を用いた「Blue Boar」に変更された。現在はホテル・チェーン「トラベロッジ」が建っている。
 リチャードがボスワースへ向かうときに渡った、ソア川にかかる橋。当時は石造りだった(図右)。現在の橋は1863年に建造されたもので、白薔薇、赤と白薔薇が合体したテューダー薔薇、白イノシシが彫られている。隣のウェスト・ブリッジの下を流れる川は後世につくられた運河。
リチャードがボスワースへ向かうときに渡った、ソア川にかかる橋。当時は石造りだった(図右)。現在の橋は1863年に建造されたもので、白薔薇、赤と白薔薇が合体したテューダー薔薇、白イノシシが彫られている。隣のウェスト・ブリッジの下を流れる川は後世につくられた運河。 戦死したリチャードの遺体が晒されたのはNewarke Street付近と言われており、レスター城の一部であったこの教会が、もっともその可能性が高いとされている。レスター城はレスター大学の一部として、グレートホールだけ現存している。
戦死したリチャードの遺体が晒されたのはNewarke Street付近と言われており、レスター城の一部であったこの教会が、もっともその可能性が高いとされている。レスター城はレスター大学の一部として、グレートホールだけ現存している。 市内で一番人気のイタリアン・ジェラート店。リチャードの発見を記念し、スペシャル・フレーバー「Richard III」(白薔薇+ベリー数種)を販売中。カップ小(£2.85)~。
市内で一番人気のイタリアン・ジェラート店。リチャードの発見を記念し、スペシャル・フレーバー「Richard III」(白薔薇+ベリー数種)を販売中。カップ小(£2.85)~。


 は主な収容所のあった場所
は主な収容所のあった場所
















 ◆ポーランドが初めて統一されたのは10世紀後半のころ。当時の首都はクラクフで、ヨーロッパでも有数の富裕な都市として発達、16世紀にはルネサンス文化が栄えるなどしたが、東のロシア、西のプロイセン(後のドイツの一部)、南のオーストリアと、まわりを強国に囲まれ、常にそれらの脅威にさらされる宿命にあった。この3国により、1772年(第一次)、93年(第二次)、95年(第三次)と三度分割され、95年の分割で、事実上、国としてのポーランドはいったん消滅してしまう。
◆ポーランドが初めて統一されたのは10世紀後半のころ。当時の首都はクラクフで、ヨーロッパでも有数の富裕な都市として発達、16世紀にはルネサンス文化が栄えるなどしたが、東のロシア、西のプロイセン(後のドイツの一部)、南のオーストリアと、まわりを強国に囲まれ、常にそれらの脅威にさらされる宿命にあった。この3国により、1772年(第一次)、93年(第二次)、95年(第三次)と三度分割され、95年の分割で、事実上、国としてのポーランドはいったん消滅してしまう。


 コペルニクス像の向かいに建っている教会。中に入ると、大きな柱がいくつか目に入るが、向かって左側手前にある柱の下には、20歳で政情不安定なポーランドを離れてから、一度も祖国の土を踏むことなく39年の生涯を終えた、ショパンの心臓が埋葬されている。第二次世界大戦時、ドイツ軍に爆破され大きな被害を被ったばかりでなく、心臓も持ち出されてしまったものの、戦後の1945年10月17日、ショパンの命日に元に戻された。
コペルニクス像の向かいに建っている教会。中に入ると、大きな柱がいくつか目に入るが、向かって左側手前にある柱の下には、20歳で政情不安定なポーランドを離れてから、一度も祖国の土を踏むことなく39年の生涯を終えた、ショパンの心臓が埋葬されている。第二次世界大戦時、ドイツ軍に爆破され大きな被害を被ったばかりでなく、心臓も持ち出されてしまったものの、戦後の1945年10月17日、ショパンの命日に元に戻された。 地動説を唱えたことで知られる、ミコワイ・コペルニクス(Mikolaj Kopernik 1473~1543)はワルシャワから180キロ ほども離れたところにある、トルンという町の出身。ポーランドを代表する偉人のひとり。
地動説を唱えたことで知られる、ミコワイ・コペルニクス(Mikolaj Kopernik 1473~1543)はワルシャワから180キロ ほども離れたところにある、トルンという町の出身。ポーランドを代表する偉人のひとり。 科学だけでなく、芸術面でもポーランド人が優れていることを証明した、フレデリック・ショパン(Fryderyk Chopin 1810~49)。自らも秀でたピアノ奏者だったショパンは、数々の名曲を残した。この博物館には、ショパンが最後に使ったといわれているピアノから、直筆の譜面、手紙まで、ショパンに関する2500点以上の資料がおさめられている。また、3階はコンサートホールとしても利用されている。
科学だけでなく、芸術面でもポーランド人が優れていることを証明した、フレデリック・ショパン(Fryderyk Chopin 1810~49)。自らも秀でたピアノ奏者だったショパンは、数々の名曲を残した。この博物館には、ショパンが最後に使ったといわれているピアノから、直筆の譜面、手紙まで、ショパンに関する2500点以上の資料がおさめられている。また、3階はコンサートホールとしても利用されている。 ワルシャワ中央駅のすぐ近くにあり、37階建て、高さ234メートルという高層ビルなのでよく目立つ。「宮殿」というよりは、「博物館」兼「一大イベント会場」ともいうべき建物で、展望台もある。中には科学技術博物館、プラネタリウム、進化博物館(恐竜の展示などもあり)のほか、ポーランドTV、コンサートホールや映画館、劇場も入っている。スターリンからの「贈り物」として、1952年から56年にかけて建造されたが、ポーランド市民からすると「おしつけられた」という意識が強いらしく、「贈り物」とは名ばかりで、ポーランド市民からの税金で作られたと信じている人が少なくないそうだ。「ソ連の建てた、ワルシャワの『墓石』」といった、ありがたくないニックネームもあるという。
ワルシャワ中央駅のすぐ近くにあり、37階建て、高さ234メートルという高層ビルなのでよく目立つ。「宮殿」というよりは、「博物館」兼「一大イベント会場」ともいうべき建物で、展望台もある。中には科学技術博物館、プラネタリウム、進化博物館(恐竜の展示などもあり)のほか、ポーランドTV、コンサートホールや映画館、劇場も入っている。スターリンからの「贈り物」として、1952年から56年にかけて建造されたが、ポーランド市民からすると「おしつけられた」という意識が強いらしく、「贈り物」とは名ばかりで、ポーランド市民からの税金で作られたと信じている人が少なくないそうだ。「ソ連の建てた、ワルシャワの『墓石』」といった、ありがたくないニックネームもあるという。 ポーランドでぜひお試しいただきたいのが、水ギョウザそっくりの「ピエロギ(Pierogi)。ひき肉、チーズ、野菜(キャベツの酢漬けが一般的)など、具はいろいろ。ただし、皮がかなり厚いため、すぐにおなかいっぱいになるのでご注意を。
ポーランドでぜひお試しいただきたいのが、水ギョウザそっくりの「ピエロギ(Pierogi)。ひき肉、チーズ、野菜(キャベツの酢漬けが一般的)など、具はいろいろ。ただし、皮がかなり厚いため、すぐにおなかいっぱいになるのでご注意を。 *オープン時間、入場料、イベントなどについては、ツーリスト・インフォメーションセンター、あるいは各スポットのホームページなどでご確認ください。
*オープン時間、入場料、イベントなどについては、ツーリスト・インフォメーションセンター、あるいは各スポットのホームページなどでご確認ください。 旧市街を囲む市壁内に入るための玄関口である、楼門。騎士たちの多くは右利きで、盾は左手、剣は右手に持つのが普通だったので、ここに入る際、騎士たちは盾で覆ってない、体の右半分をフロリアンスカ門の衛兵(いつでも矢を放てるように構えていた)に見せて入場するよう、入り口の角度が設定してあったという。
旧市街を囲む市壁内に入るための玄関口である、楼門。騎士たちの多くは右利きで、盾は左手、剣は右手に持つのが普通だったので、ここに入る際、騎士たちは盾で覆ってない、体の右半分をフロリアンスカ門の衛兵(いつでも矢を放てるように構えていた)に見せて入場するよう、入り口の角度が設定してあったという。
 クラクフに数ある教会の中でも、ひときわ目立つ荘厳な教会。1222年建造で、中央市場広場に面してそびえる。昔々、モンゴル軍がクラクフに攻め入ろうとした時、敵が来たことを知らせるために、ある兵士がこの教会の塔の上でラッパを吹き鳴らした。このラッパ手は、まもなくモンゴル兵の放った矢に貫かれて絶命するが、そのラッパ手の死を悼んで、今でも1時間ごとにラッパが吹き鳴らされる。
クラクフに数ある教会の中でも、ひときわ目立つ荘厳な教会。1222年建造で、中央市場広場に面してそびえる。昔々、モンゴル軍がクラクフに攻め入ろうとした時、敵が来たことを知らせるために、ある兵士がこの教会の塔の上でラッパを吹き鳴らした。このラッパ手は、まもなくモンゴル兵の放った矢に貫かれて絶命するが、そのラッパ手の死を悼んで、今でも1時間ごとにラッパが吹き鳴らされる。
 教会の外に聖人たちがずらりと並んでいるのは、中が小さすぎるため、というジョークがささやかれる教会だが、実際にはかなり大きく、かつ荘厳。
教会の外に聖人たちがずらりと並んでいるのは、中が小さすぎるため、というジョークがささやかれる教会だが、実際にはかなり大きく、かつ荘厳。 歴代ポーランド王の居城として使われた場所。旧王宮部分にある、王宮博物館(Komnaty Krolewskie)、18世紀まで代々、ポーランド王の戴冠式が行われた大聖堂(Katedra Wawelska)、金色のドームが目印のジグムント・チャペル(Kaplica Zygmuntowska)、ポーランド最大の鐘がつるされているジグムント塔(Wieza Zygmuntowska)など、見どころが多い。なお、このジグムント塔の鐘は、宗教上、あるいは国政上、重要なことが起こった時にしか鳴らされないことになっている。
歴代ポーランド王の居城として使われた場所。旧王宮部分にある、王宮博物館(Komnaty Krolewskie)、18世紀まで代々、ポーランド王の戴冠式が行われた大聖堂(Katedra Wawelska)、金色のドームが目印のジグムント・チャペル(Kaplica Zygmuntowska)、ポーランド最大の鐘がつるされているジグムント塔(Wieza Zygmuntowska)など、見どころが多い。なお、このジグムント塔の鐘は、宗教上、あるいは国政上、重要なことが起こった時にしか鳴らされないことになっている。
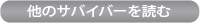






 Tottenham Court Road
Tottenham Court Road
 1905年のオープン以来、英国最大の品揃えを誇る本屋。吹き抜けになった地上7階(6th floor)、地下1階建ての店内にある、すべての書棚を並べると全長6.5キロにもなると言われるが、本のセレクションはそんな大型店にありがちな「広く浅く」からは程遠く、ツボを押さえた専門書も並ぶ。2014年の移転でカフェ、ギャラリー、文房具売り場なども充実。老舗というだけでなく、これからあるべき本屋の姿を追求している店だ。オリジナル・エコバッグやトラベル・マグのほか、「Foyalty Card」というポイント・カード=写真左上=も人気(£1につき4ポイント加算、1ポイントは1p相当)。
1905年のオープン以来、英国最大の品揃えを誇る本屋。吹き抜けになった地上7階(6th floor)、地下1階建ての店内にある、すべての書棚を並べると全長6.5キロにもなると言われるが、本のセレクションはそんな大型店にありがちな「広く浅く」からは程遠く、ツボを押さえた専門書も並ぶ。2014年の移転でカフェ、ギャラリー、文房具売り場なども充実。老舗というだけでなく、これからあるべき本屋の姿を追求している店だ。オリジナル・エコバッグやトラベル・マグのほか、「Foyalty Card」というポイント・カード=写真左上=も人気(£1につき4ポイント加算、1ポイントは1p相当)。
 世界最大級の希少アンティーク本を取り扱う、1853年創業の古書店。バークリー・スクエアに面したジョージ・カニング首相(1770~1827年)の自宅だった店舗(50 Berkeley Square, W1J 5BA)=写真=から昨年移転し、スペースを縮小して今年中に再オープンの予定(事前予約をすれば、再オープン前でも来店可能)。本のほかに、作家のバーナード・ショー(£425)やオスカー・ワイルド(£3950)など、著名人の実筆の手紙も展示販売されているので、博物館感覚で見学できそうだ。ただし店舗という雰囲気はないので、本を手に取る前に一声かけたほうがいいだろう。
世界最大級の希少アンティーク本を取り扱う、1853年創業の古書店。バークリー・スクエアに面したジョージ・カニング首相(1770~1827年)の自宅だった店舗(50 Berkeley Square, W1J 5BA)=写真=から昨年移転し、スペースを縮小して今年中に再オープンの予定(事前予約をすれば、再オープン前でも来店可能)。本のほかに、作家のバーナード・ショー(£425)やオスカー・ワイルド(£3950)など、著名人の実筆の手紙も展示販売されているので、博物館感覚で見学できそうだ。ただし店舗という雰囲気はないので、本を手に取る前に一声かけたほうがいいだろう。
 英国各地に支店を持つ大型書店ウォーターストーンズ。数少なからぬ本屋が次々に店じまいする中、学生街では学術書、シティではビジネス書、観光地ではガイドブックやギフト商品等、立地に合わせて柔軟に品揃えを変えることで生き残ってきた。本店のピカデリー店は、有名デパート「シンプソン・ロンドン」跡を利用しており、地上6階(5th floor、中2階もあり)、地下1階建てという「本のデパート」。人気作家のサイン会が開かれることでも知られる。地下1階と中2階=写真=にカフェ、6階には眺めのいいバー&レストランがあり、ここではアフタヌーンティー(£14.95)も楽しめる。
英国各地に支店を持つ大型書店ウォーターストーンズ。数少なからぬ本屋が次々に店じまいする中、学生街では学術書、シティではビジネス書、観光地ではガイドブックやギフト商品等、立地に合わせて柔軟に品揃えを変えることで生き残ってきた。本店のピカデリー店は、有名デパート「シンプソン・ロンドン」跡を利用しており、地上6階(5th floor、中2階もあり)、地下1階建てという「本のデパート」。人気作家のサイン会が開かれることでも知られる。地下1階と中2階=写真=にカフェ、6階には眺めのいいバー&レストランがあり、ここではアフタヌーンティー(£14.95)も楽しめる。 英国各地に支店を持つ大型書店ウォーターストーンズ。数少なからぬ本屋が次々に店じまいする中、学生街では学術書、シティではビジネス書、観光地ではガイドブックやギフト商品等、立地に合わせて柔軟に品揃えを変えることで生き残ってきた。本店のピカデリー店は、有名デパート「シンプソン・ロンドン」跡を利用しており、地上6階(5th floor、中2階もあり)、地下1階建てという「本のデパート」。人気作家のサイン会が開かれることでも知られる。地下1階と中2階=写真=にカフェ、6階には眺めのいいバー&レストランがあり、ここではアフタヌーンティー(£14.95)も楽しめる。
英国各地に支店を持つ大型書店ウォーターストーンズ。数少なからぬ本屋が次々に店じまいする中、学生街では学術書、シティではビジネス書、観光地ではガイドブックやギフト商品等、立地に合わせて柔軟に品揃えを変えることで生き残ってきた。本店のピカデリー店は、有名デパート「シンプソン・ロンドン」跡を利用しており、地上6階(5th floor、中2階もあり)、地下1階建てという「本のデパート」。人気作家のサイン会が開かれることでも知られる。地下1階と中2階=写真=にカフェ、6階には眺めのいいバー&レストランがあり、ここではアフタヌーンティー(£14.95)も楽しめる。

 労働運動、女性解放運動、人権…。ジェレミー・コービン氏が労働党党首になったことで、にわかに活気付いた英国の社会主義やその歴史について知りたい場合は、この本屋をおいて他にないだろう。といっても、店内にはジャズが流れ、意外にも堅苦しい雰囲気はない。政治スローガンを印刷したバッジやマグカップ、ポストカード、エコバッグのほか、児童書コーナーには環境問題について考える絵本なども置かれている。
労働運動、女性解放運動、人権…。ジェレミー・コービン氏が労働党党首になったことで、にわかに活気付いた英国の社会主義やその歴史について知りたい場合は、この本屋をおいて他にないだろう。といっても、店内にはジャズが流れ、意外にも堅苦しい雰囲気はない。政治スローガンを印刷したバッジやマグカップ、ポストカード、エコバッグのほか、児童書コーナーには環境問題について考える絵本なども置かれている。 ロンドン北部を走る運河上に浮かぶ、小さなボートで経営されている古本屋。まっすぐ立つこともすれ違うこともできないような小さな店内には、奇妙なオブジェや写真も飾られ、まるで子供の頃読んだ物語の舞台がそのまま再現されたかのよう。基本的にはキングス・クロス周辺の運河に停泊しているが、夏季などは2週間ごとに場所を移動することも多く、また雨天の場合や移動日の前後なども休業する可能性が高いので、当日にフェイスブック等で確認する必要あり。付近のカナル・パスの散歩も楽しめる。
ロンドン北部を走る運河上に浮かぶ、小さなボートで経営されている古本屋。まっすぐ立つこともすれ違うこともできないような小さな店内には、奇妙なオブジェや写真も飾られ、まるで子供の頃読んだ物語の舞台がそのまま再現されたかのよう。基本的にはキングス・クロス周辺の運河に停泊しているが、夏季などは2週間ごとに場所を移動することも多く、また雨天の場合や移動日の前後なども休業する可能性が高いので、当日にフェイスブック等で確認する必要あり。付近のカナル・パスの散歩も楽しめる。
 13 Blenheim Crescent, W11 2EE
13 Blenheim Crescent, W11 2EE  1999年制作の映画『ノッティングヒルの恋人』=写真上=の舞台ともなった本屋。映画はヒュー・グラント扮する本屋の店主と、ジュリア・ロバーツ扮する人気ハリウッド女優の恋を描いたロマンティック・コメディ。15年以上前の作品だが、取材時も同店の前で記念撮影をする女性たちの姿があり、今も「あの映画の本屋」として著名であることを伺わせる。以前は旅行書専門の「Travel Bookshop」という名だったが、オーナーが変わり今に至る。オリジナル・エコバッグ(3種類、£2.99~£12.99)あり。
1999年制作の映画『ノッティングヒルの恋人』=写真上=の舞台ともなった本屋。映画はヒュー・グラント扮する本屋の店主と、ジュリア・ロバーツ扮する人気ハリウッド女優の恋を描いたロマンティック・コメディ。15年以上前の作品だが、取材時も同店の前で記念撮影をする女性たちの姿があり、今も「あの映画の本屋」として著名であることを伺わせる。以前は旅行書専門の「Travel Bookshop」という名だったが、オーナーが変わり今に至る。オリジナル・エコバッグ(3種類、£2.99~£12.99)あり。

 やや不便な場所にあるものの、品数の多さと、フレンドリーな目利きスタッフがいるおかげで、1974年のオープン以来多くの賞を受賞してきた児童書専門店。各国の絵本から、高学年向け児童書までが揃う。地元の小学校と提携し、原作者による朗読のイベントを手配するといったことも行っている。また、毎週木曜の午前11時からは、店内で子供のために絵本の読み聞かせの時間を設けている。
やや不便な場所にあるものの、品数の多さと、フレンドリーな目利きスタッフがいるおかげで、1974年のオープン以来多くの賞を受賞してきた児童書専門店。各国の絵本から、高学年向け児童書までが揃う。地元の小学校と提携し、原作者による朗読のイベントを手配するといったことも行っている。また、毎週木曜の午前11時からは、店内で子供のために絵本の読み聞かせの時間を設けている。
 本の好きな男性2人が1999年、セシル・コートに開店。著者のサイン入り初版本を新旧を問わずに扱い、その数は現在約2万5000冊! 読書を愛する人だけではなく、価値が上がっていく本を探すコレクターたちによっても支えられている。
本の好きな男性2人が1999年、セシル・コートに開店。著者のサイン入り初版本を新旧を問わずに扱い、その数は現在約2万5000冊! 読書を愛する人だけではなく、価値が上がっていく本を探すコレクターたちによっても支えられている。 「ノッティングヒル・ブックショップ」の通りを隔てた斜め前にある、料理本専門店。1983年のオープン以来、プロから料理好きのアマチュア、食べることが大好きな人などが通う、宝箱のような本屋だ。時代を超えたベストセラーから最新刊まで、文字通り「世界中の料理」を紹介する本が集結している。奥のカフェでは本のレシピを試作したものを出したり、ワークショップも開催されたりする。
「ノッティングヒル・ブックショップ」の通りを隔てた斜め前にある、料理本専門店。1983年のオープン以来、プロから料理好きのアマチュア、食べることが大好きな人などが通う、宝箱のような本屋だ。時代を超えたベストセラーから最新刊まで、文字通り「世界中の料理」を紹介する本が集結している。奥のカフェでは本のレシピを試作したものを出したり、ワークショップも開催されたりする。 トテナム・コート・ロード駅への乗り入れによる、駅周辺の拡張工事をかろうじて免れたソーホー・エリアにあり、賭け屋の上階に位置する、写真とファッション専門書店。エキセントリックな魅力でソーホーの主のような存在だった書店オーナーが2012年に死去したものの、有志たちによって引き継がれた。ギャラリーも併設。
トテナム・コート・ロード駅への乗り入れによる、駅周辺の拡張工事をかろうじて免れたソーホー・エリアにあり、賭け屋の上階に位置する、写真とファッション専門書店。エキセントリックな魅力でソーホーの主のような存在だった書店オーナーが2012年に死去したものの、有志たちによって引き継がれた。ギャラリーも併設。
 ロンドンから車で約3時間半、ウェールズのポーイス(Powys)にあるヘイ・オン・ワイ(Hay-on-Wye)の町は、古書店街として知られている。1960年代から徐々に形成され、現在は30軒以上の古書店が立ち並ぶ。ヘイ・オン・ワイは交通も不便で、人口は約1,500人の小さな町だ。古書店街といえば、通常学生の多い都市部にできるのが一般的だが、なぜこのようなところに出現したのだろうか。
ロンドンから車で約3時間半、ウェールズのポーイス(Powys)にあるヘイ・オン・ワイ(Hay-on-Wye)の町は、古書店街として知られている。1960年代から徐々に形成され、現在は30軒以上の古書店が立ち並ぶ。ヘイ・オン・ワイは交通も不便で、人口は約1,500人の小さな町だ。古書店街といえば、通常学生の多い都市部にできるのが一般的だが、なぜこのようなところに出現したのだろうか。
![いざというときに役に立つ【ファーストエイド】基本の「キ」 [First Aid]](http://www.japanjournals.com//images/stories/survivor/160204firstaid/ttl.jpg)











 ダラム近郊の町、シーハムの海岸線にたたずむ「シーハムホール」は、バイロンの妻アナベラの実家、ミルバンク家が所有する邸宅のひとつであり、1815年1月2日、バイロンとアナベラが結婚式を挙げている。現在はジョージア朝の伝統とモダンな快適さを併せ持つ5つ星ホテルとなっているが、挙式した部屋は「バイロン・ルーム」と名付けられ=写真下、会議などで使用する多目的ルームとなっている。
ダラム近郊の町、シーハムの海岸線にたたずむ「シーハムホール」は、バイロンの妻アナベラの実家、ミルバンク家が所有する邸宅のひとつであり、1815年1月2日、バイロンとアナベラが結婚式を挙げている。現在はジョージア朝の伝統とモダンな快適さを併せ持つ5つ星ホテルとなっているが、挙式した部屋は「バイロン・ルーム」と名付けられ=写真下、会議などで使用する多目的ルームとなっている。



 1980年12月10日、米国防総省はエイダの功績に敬意を表し、新しいコンピューター・プログラミング言語を「エイダ(Ada)」と名づけた。MIL規格番号(MIL-STD-1815)は、彼女の生年にちなんでおり、発表日はエイダの誕生日であった。「Ada」は多彩な言語機能と高度な言語体系を持ち、航空機のボーイング777や、F-22戦闘機=写真=の制御ソフトウェアは「Ada」によって書かれているという。飛行に憧れた少女の夢は、150年を経て叶ったと言えるのかもしれない。
1980年12月10日、米国防総省はエイダの功績に敬意を表し、新しいコンピューター・プログラミング言語を「エイダ(Ada)」と名づけた。MIL規格番号(MIL-STD-1815)は、彼女の生年にちなんでおり、発表日はエイダの誕生日であった。「Ada」は多彩な言語機能と高度な言語体系を持ち、航空機のボーイング777や、F-22戦闘機=写真=の制御ソフトウェアは「Ada」によって書かれているという。飛行に憧れた少女の夢は、150年を経て叶ったと言えるのかもしれない。



 当時の東海道筋で、生麦村のちょうど中間点にあたる、村田屋勘左衛門の営む質屋兼豆腐屋の前で事件は起こった。現在は、個人宅の前に説明板=写真=が設置されている。
当時の東海道筋で、生麦村のちょうど中間点にあたる、村田屋勘左衛門の営む質屋兼豆腐屋の前で事件は起こった。現在は、個人宅の前に説明板=写真=が設置されている。 ヘボン博士の診療所だった場所。
ヘボン博士の診療所だった場所。 英国の陸軍中佐として活躍するが、1837年に退役して外交官となる。清国の英国公使館書記官を経て、62年に日本の公使館書記官として来日。同年、休暇で帰国中のオールコックに代わって公使を務める。在任中、第二次東禅寺事件(松本藩藩士による暗殺未遂事件)で命を狙われる危機に遭い、さらに生麦事件、薩英戦争の勃発と多忙を極めるが、本国と連携を保ち、冷静に対処する。64年にオールコック公使帰任をもって帰国。
英国の陸軍中佐として活躍するが、1837年に退役して外交官となる。清国の英国公使館書記官を経て、62年に日本の公使館書記官として来日。同年、休暇で帰国中のオールコックに代わって公使を務める。在任中、第二次東禅寺事件(松本藩藩士による暗殺未遂事件)で命を狙われる危機に遭い、さらに生麦事件、薩英戦争の勃発と多忙を極めるが、本国と連携を保ち、冷静に対処する。64年にオールコック公使帰任をもって帰国。
 英国公使館付医師として1861年に来日。生麦事件の負傷者の治療や検死にあたった後、薩英戦争で英国艦船に同乗。戊辰戦争時には相国寺に薩軍臨時病院を設置し、負傷者の手当てに従事。1869年、31歳の若さで東京医学校(のちの東京大学医学部)の院長に就任するも翌年に退任、西郷隆盛や大久保利通らの斡旋により、鹿児島医学校(のちの鹿児島大学医学部)に赴任。81年に帰国するまで日本の医療システムの構築に多大な功績を残す。通訳として活躍したアーネスト・サトウ(詳細は次号参照のこと)とは生涯を通じて親友同士。
英国公使館付医師として1861年に来日。生麦事件の負傷者の治療や検死にあたった後、薩英戦争で英国艦船に同乗。戊辰戦争時には相国寺に薩軍臨時病院を設置し、負傷者の手当てに従事。1869年、31歳の若さで東京医学校(のちの東京大学医学部)の院長に就任するも翌年に退任、西郷隆盛や大久保利通らの斡旋により、鹿児島医学校(のちの鹿児島大学医学部)に赴任。81年に帰国するまで日本の医療システムの構築に多大な功績を残す。通訳として活躍したアーネスト・サトウ(詳細は次号参照のこと)とは生涯を通じて親友同士。

 島津氏27代当主、斉興(なりおき)の五男。長男である斉彬(なりあきら)との家督争いに敗れるも、1858年に斉彬が急死し、その遺言によって自身の長男、茂久(もちひさ=後に忠義)が29代当主の座に就くと国父となり、事実上、藩の実権を握る。過激な攘夷論者を取り締まり、公武合体運動を推進。西郷隆盛とソリが合わず、長きにわたり確執を抱えていた。
島津氏27代当主、斉興(なりおき)の五男。長男である斉彬(なりあきら)との家督争いに敗れるも、1858年に斉彬が急死し、その遺言によって自身の長男、茂久(もちひさ=後に忠義)が29代当主の座に就くと国父となり、事実上、藩の実権を握る。過激な攘夷論者を取り締まり、公武合体運動を推進。西郷隆盛とソリが合わず、長きにわたり確執を抱えていた。
 薩摩藩士、有村仁左衛門兼善の長男。生麦事件では、もはや助かる見込みのないリチャードソンに「武士の情け」をもって止めを刺す。当時30歳。戊辰戦争では東海道先鋒総督参謀として活躍。後に子爵となり、奈良県知事、京都府知事を歴任。長女の鉄子は東郷平八郎の妻。左の写真は、67歳の時のもの(1899年撮影)。
薩摩藩士、有村仁左衛門兼善の長男。生麦事件では、もはや助かる見込みのないリチャードソンに「武士の情け」をもって止めを刺す。当時30歳。戊辰戦争では東海道先鋒総督参謀として活躍。後に子爵となり、奈良県知事、京都府知事を歴任。長女の鉄子は東郷平八郎の妻。左の写真は、67歳の時のもの(1899年撮影)。




 島津久光に手腕を認められて側近となり、1862年、弱冠28歳で家老に昇進。藩政改革に積極的に取り組み、諸藩と交易することで藩の財政を豊かにし、軍事力を拡大するなど、藩の活性化、近代化に大きく貢献する。薩英戦争では久光と藩主・茂久(維新後は忠義)の側近として戦いの総指揮にあたり、戦後は英国と薩摩藩の友好に尽力。卓越した政治力で朝廷、幕府、諸藩との連絡、交渉役を務め、同年生まれの坂本龍馬とも意気投合して薩長同盟実現のために奔走する。67年には将軍徳川慶喜に大政奉還を進言。明治新政府においては参与や外交事務掛などの要職を歴任するが、69年、病のため退任。70年に36歳の若さで惜しまれながらも病死する。「幻の宰相」とも称され、明治維新の陰の功労者と言われる。
島津久光に手腕を認められて側近となり、1862年、弱冠28歳で家老に昇進。藩政改革に積極的に取り組み、諸藩と交易することで藩の財政を豊かにし、軍事力を拡大するなど、藩の活性化、近代化に大きく貢献する。薩英戦争では久光と藩主・茂久(維新後は忠義)の側近として戦いの総指揮にあたり、戦後は英国と薩摩藩の友好に尽力。卓越した政治力で朝廷、幕府、諸藩との連絡、交渉役を務め、同年生まれの坂本龍馬とも意気投合して薩長同盟実現のために奔走する。67年には将軍徳川慶喜に大政奉還を進言。明治新政府においては参与や外交事務掛などの要職を歴任するが、69年、病のため退任。70年に36歳の若さで惜しまれながらも病死する。「幻の宰相」とも称され、明治維新の陰の功労者と言われる。
 英国の外交官。スウェーデン人の父と英国人の母の間に生まれる。1862年、弱冠19歳で、かねてから興味を抱いていた日本に通訳見習いとして赴任。到着6日後に生麦事件が起こる。その後の薩英戦争から下関戦争、戊辰戦争にいたるまで、激動の幕末~近代日本の変革をつぶさに体験。68年からは書記官となり、83年まで滞在して一度日本を離れるが、95年に英国公使として再来日し、1900年まで滞在する。日本滞在歴は計25年に及び、「一外交官の見た明治維新」をはじめ多数の著作を残しているほか、日本学者として日本アジア協会の設立にも尽力し、神道の研究も行っている。ちなみに東京の英国大使館前の桜並木は、1898年にサトウが植樹して寄贈したもの。またサトウという姓はスラヴ系の希少姓で、日本の姓とは全く関係なかったが、この名前のお陰で日本社会に溶け込みやすかったと本人が語っている。
英国の外交官。スウェーデン人の父と英国人の母の間に生まれる。1862年、弱冠19歳で、かねてから興味を抱いていた日本に通訳見習いとして赴任。到着6日後に生麦事件が起こる。その後の薩英戦争から下関戦争、戊辰戦争にいたるまで、激動の幕末~近代日本の変革をつぶさに体験。68年からは書記官となり、83年まで滞在して一度日本を離れるが、95年に英国公使として再来日し、1900年まで滞在する。日本滞在歴は計25年に及び、「一外交官の見た明治維新」をはじめ多数の著作を残しているほか、日本学者として日本アジア協会の設立にも尽力し、神道の研究も行っている。ちなみに東京の英国大使館前の桜並木は、1898年にサトウが植樹して寄贈したもの。またサトウという姓はスラヴ系の希少姓で、日本の姓とは全く関係なかったが、この名前のお陰で日本社会に溶け込みやすかったと本人が語っている。
 鹿児島城下の下加冶屋町で薩摩藩の下士として生まれる。西郷隆盛とは幼なじみ。藩内若手改革派、精忠組の中心人物となり、島津久光のもとで公武合体運動を推進。幕府の長州征伐が失敗に終わった後、西郷らと倒幕運動を進め、岩倉具視らとともに王政復古のクーデターを敢行。明治維新後の1869年には参議に就任し、版籍奉還、廃藩置県など中央集権体制確立を行い、71年には大蔵卿に就任。特命全権副使として岩倉遣外使節団に随行する。帰国後は内務省を設置し、初代内務卿となって地租改正や徴兵令などを実施する。西南戦争では政府軍を指揮し、鹿児島士族の反乱を鎮圧。78年5月14日、石川県士族の島田一郎ら不平士族により紀尾井坂で暗殺される。享年47。
鹿児島城下の下加冶屋町で薩摩藩の下士として生まれる。西郷隆盛とは幼なじみ。藩内若手改革派、精忠組の中心人物となり、島津久光のもとで公武合体運動を推進。幕府の長州征伐が失敗に終わった後、西郷らと倒幕運動を進め、岩倉具視らとともに王政復古のクーデターを敢行。明治維新後の1869年には参議に就任し、版籍奉還、廃藩置県など中央集権体制確立を行い、71年には大蔵卿に就任。特命全権副使として岩倉遣外使節団に随行する。帰国後は内務省を設置し、初代内務卿となって地租改正や徴兵令などを実施する。西南戦争では政府軍を指揮し、鹿児島士族の反乱を鎮圧。78年5月14日、石川県士族の島田一郎ら不平士族により紀尾井坂で暗殺される。享年47。
 英国のスーパーの果物売り場で、時折目にすることがある「satsuma」。実はこれは、薩英戦争後の賠償交渉がスムーズに運んだことに対し、薩摩藩が英国側に感謝のしるしとしてミカンを進呈したことに由来している。代理公使ニールが本国のラッセル外務大臣に送った書状に「カゴいっぱいのミカンが戦艦ユーリアラス号に持ち込まれた」と記載されているのだそう。その後、米国、スペインなどにも苗木が薩摩から輸出され、各国で栽培されるようになった。
英国のスーパーの果物売り場で、時折目にすることがある「satsuma」。実はこれは、薩英戦争後の賠償交渉がスムーズに運んだことに対し、薩摩藩が英国側に感謝のしるしとしてミカンを進呈したことに由来している。代理公使ニールが本国のラッセル外務大臣に送った書状に「カゴいっぱいのミカンが戦艦ユーリアラス号に持ち込まれた」と記載されているのだそう。その後、米国、スペインなどにも苗木が薩摩から輸出され、各国で栽培されるようになった。
 神奈川県横浜市の鶴見区生麦にある、個人宅を改造してつくられた資料館。酒類商、株式会社神田屋に勤めていた浅海武夫さんが1976年より仕事の傍ら、生麦事件に関する資料や文献を集め始め、1994年に自費で設立した。館内では浅海さんが情熱をかけて集めた1000点におよぶ所蔵資料のうち、約150点が閲覧できる。事件の様子が綴られた当時の文書や、オランダの博物館から10ヵ月かかって取り寄せた事件に関する写真など、貴重な資料を多数展示。「神田屋酒の記念館」を併設。
神奈川県横浜市の鶴見区生麦にある、個人宅を改造してつくられた資料館。酒類商、株式会社神田屋に勤めていた浅海武夫さんが1976年より仕事の傍ら、生麦事件に関する資料や文献を集め始め、1994年に自費で設立した。館内では浅海さんが情熱をかけて集めた1000点におよぶ所蔵資料のうち、約150点が閲覧できる。事件の様子が綴られた当時の文書や、オランダの博物館から10ヵ月かかって取り寄せた事件に関する写真など、貴重な資料を多数展示。「神田屋酒の記念館」を併設。








 「彼らのような夫婦になりたい」
「彼らのような夫婦になりたい」
 愛犬コーギーへのイタズラは禁物!
愛犬コーギーへのイタズラは禁物! 「悩ましきX'masプレゼント」
「悩ましきX'masプレゼント」
 「祖母というより女王は上司」
「祖母というより女王は上司」
 われを忘れるほどの競馬好き
われを忘れるほどの競馬好き 「不必要な電気は消すように」
「不必要な電気は消すように」
 密かなアーセナル・ファン!?
密かなアーセナル・ファン!? バッグの中には何が?
バッグの中には何が?
 あだ名は「ガンガン」
あだ名は「ガンガン」 女王はスピード狂!?
女王はスピード狂!? 歴史ドラマの間違い探しはやめられない!
歴史ドラマの間違い探しはやめられない!
 物まねが得意?
物まねが得意? サッチャー首相とファッション対立?
サッチャー首相とファッション対立?
 秘密のサイン
秘密のサイン ワードローブの29%はブルー
ワードローブの29%はブルー
 7:30 起床
7:30 起床 8:30 朝食
8:30 朝食 9:00 公務開始
9:00 公務開始 13:00 昼食
13:00 昼食 17:00 ハイ・ティー
17:00 ハイ・ティー レーズン、オレンジ・ピールなどを用いたスコットランド・ダンディー発祥のフルーツ・ケーキ。一般的なフルーツ・ケーキに使われる砂糖漬けのチェリーが嫌いだったスコットランド女王メアリーのために、作られたのが始まりとされる。
レーズン、オレンジ・ピールなどを用いたスコットランド・ダンディー発祥のフルーツ・ケーキ。一般的なフルーツ・ケーキに使われる砂糖漬けのチェリーが嫌いだったスコットランド女王メアリーのために、作られたのが始まりとされる。 18:30 再び公務
18:30 再び公務 19:30リラックス
19:30リラックス エリザベス女王が生まれたのは4月21日だが、この日とは別に、公式の誕生日がある。18世紀、君主の公式誕生日は毎年6月の第2土曜日と定められ、以来この日にパレードを行い大々的にお祝いするのが伝統となった。ちなみに、6月が選ばれたのは「晴天になる確率が高いから」といわれている。今年の公式誕生日は6月11日。
エリザベス女王が生まれたのは4月21日だが、この日とは別に、公式の誕生日がある。18世紀、君主の公式誕生日は毎年6月の第2土曜日と定められ、以来この日にパレードを行い大々的にお祝いするのが伝統となった。ちなみに、6月が選ばれたのは「晴天になる確率が高いから」といわれている。今年の公式誕生日は6月11日。 公式誕生日の前日、王室関係者が集まり感謝の礼拝を行う。この日のために新たに作曲されたという聖歌が、大聖堂付属の合唱団によって披露される。作曲はジュディス・ウィアー、歌詞は、女王の誕生した年に詩人ロバート・ブリッジズによって作られた詩篇を元にしているそう。一般の人々は聖堂内への入場はできないが、この模様はBBC1で放送される。なお、この日は95歳となるエディンバラ公の誕生日でもあり、ダブルでおめでたい1日。
公式誕生日の前日、王室関係者が集まり感謝の礼拝を行う。この日のために新たに作曲されたという聖歌が、大聖堂付属の合唱団によって披露される。作曲はジュディス・ウィアー、歌詞は、女王の誕生した年に詩人ロバート・ブリッジズによって作られた詩篇を元にしているそう。一般の人々は聖堂内への入場はできないが、この模様はBBC1で放送される。なお、この日は95歳となるエディンバラ公の誕生日でもあり、ダブルでおめでたい1日。 王室一家のほか、英国の政財官各界の賓客を迎えて行われる式典、「トゥルーピング・ザ・カラー(Trooping the Colour)」(軍旗敬礼分裂式)。英王室軍による華麗な軍楽パレードが有名で、バッキンガム宮殿から式典の会場であるホースガーズ・パレードまで、式典の終了後には再びバッキンガム宮殿までを大行進する。宮殿に戻った王室一家は、英空軍による祝賀飛行を観覧するため、午後1時頃に宮殿のバルコニーに姿を表す。沿道に設えられたパレード見学席のチケットはすでに売り切れだが、宮殿前の大通りザ・マルからパレードを眺めることも可能なほか、BBCでも放送予定。
王室一家のほか、英国の政財官各界の賓客を迎えて行われる式典、「トゥルーピング・ザ・カラー(Trooping the Colour)」(軍旗敬礼分裂式)。英王室軍による華麗な軍楽パレードが有名で、バッキンガム宮殿から式典の会場であるホースガーズ・パレードまで、式典の終了後には再びバッキンガム宮殿までを大行進する。宮殿に戻った王室一家は、英空軍による祝賀飛行を観覧するため、午後1時頃に宮殿のバルコニーに姿を表す。沿道に設えられたパレード見学席のチケットはすでに売り切れだが、宮殿前の大通りザ・マルからパレードを眺めることも可能なほか、BBCでも放送予定。


 1893年9月4日にポターが元家庭教師の息子(ノエル・ムーア)に宛てて書いた絵手紙が原型であるため、この日がピーター・ラビットの誕生日とされている。
1893年9月4日にポターが元家庭教師の息子(ノエル・ムーア)に宛てて書いた絵手紙が原型であるため、この日がピーター・ラビットの誕生日とされている。

 ポター(レネー・ゼルウィガー演)が絵本作家になるまでを描いた、2006年製作の作品。本作は、婚約者ノーマン・ウォーン(ユアン・マクレガー演)との死別という悲しみを乗り越え、印税で購入したヒル・トップ農場で創作に専念し始めるところで終わる。
ポター(レネー・ゼルウィガー演)が絵本作家になるまでを描いた、2006年製作の作品。本作は、婚約者ノーマン・ウォーン(ユアン・マクレガー演)との死別という悲しみを乗り越え、印税で購入したヒル・トップ農場で創作に専念し始めるところで終わる。

 産業革命で、都市や農村のあり方が大きく変わりつつあった1894年。美しい田園風景や歴史的な価値がある建物を、国民の『共通遺産』として残そうと、3人の有志たちによって設立されたのが「ナショナル・トラスト」である。
産業革命で、都市や農村のあり方が大きく変わりつつあった1894年。美しい田園風景や歴史的な価値がある建物を、国民の『共通遺産』として残そうと、3人の有志たちによって設立されたのが「ナショナル・トラスト」である。




 日本のスポーツ史において、初めて五輪でメダルを獲得した競技が、実はテニス。1920年アントワープ大会で、熊谷一弥(男子シングルス)、熊谷一弥、柏尾誠一郎組(男子ダブルス)が銀メダルをもたらした。それから1世紀ほどの時を経て、日本テニス界のエース、錦織圭(26)が男子シングルスで金メダルを狙う。ただ、世界ランク6位の錦織は、6月のウィンブルドン選手権で痛めた左脇腹の状態が心配される。男子シングルスには、錦織含む3選手が出場する。
日本のスポーツ史において、初めて五輪でメダルを獲得した競技が、実はテニス。1920年アントワープ大会で、熊谷一弥(男子シングルス)、熊谷一弥、柏尾誠一郎組(男子ダブルス)が銀メダルをもたらした。それから1世紀ほどの時を経て、日本テニス界のエース、錦織圭(26)が男子シングルスで金メダルを狙う。ただ、世界ランク6位の錦織は、6月のウィンブルドン選手権で痛めた左脇腹の状態が心配される。男子シングルスには、錦織含む3選手が出場する。 ゴルフの普及を目的に、112年ぶりに正式種目に復活するも、治安やジカ熱への懸念などを理由に、豪ジェイソン・デイ、英ロリー・マキロイら男子トップ4が出場を辞退。日本勢も松山英樹(24)と谷原秀人(37)が辞退しており、男子は池田勇太(30)、片山晋呉(43)、女子は野村敏京(はるきょう、23)、大山志保(39) が出場する。
ゴルフの普及を目的に、112年ぶりに正式種目に復活するも、治安やジカ熱への懸念などを理由に、豪ジェイソン・デイ、英ロリー・マキロイら男子トップ4が出場を辞退。日本勢も松山英樹(24)と谷原秀人(37)が辞退しており、男子は池田勇太(30)、片山晋呉(43)、女子は野村敏京(はるきょう、23)、大山志保(39) が出場する。

 開催期間 : 8月5日(金)~21日(日)
開催期間 : 8月5日(金)~21日(日) 遠く離れたリオまで足を運ぶことは難しいかもしれないが、英国テレビ史上、最も成功を収めたというロンドン大会同様、BBCが総力を挙げて現地から中継する。TV(BBC1、2、4/英国時間で毎日午後1時~翌朝4時ごろ)、BBCレッド・ボタン、ラジオ、オンライン(
遠く離れたリオまで足を運ぶことは難しいかもしれないが、英国テレビ史上、最も成功を収めたというロンドン大会同様、BBCが総力を挙げて現地から中継する。TV(BBC1、2、4/英国時間で毎日午後1時~翌朝4時ごろ)、BBCレッド・ボタン、ラジオ、オンライン( モハメド・ファラー
モハメド・ファラー  トム・デイリー
トム・デイリー ジェシカ・エニス=ヒル
ジェシカ・エニス=ヒル ブラッドリー・ウィギンズ
ブラッドリー・ウィギンズ ネイマール
ネイマール ウサイン・ボルト
ウサイン・ボルト


 1863年の開通当時の面影をそのまま残したハマースミス・シティ線、サークル線ホームは必見。蒸気機関車が通ったというだけある高い天井と幅広い線路、重厚な煉瓦の壁に圧倒される。
1863年の開通当時の面影をそのまま残したハマースミス・シティ線、サークル線ホームは必見。蒸気機関車が通ったというだけある高い天井と幅広い線路、重厚な煉瓦の壁に圧倒される。 一方、ベーカー・ストリートといえばこの人、名探偵シャーロック・ホームズ。ベーカールー線のホームや通路ではホームズを象ったデザインのタイル壁画に出会うことができる。また、中央切符売り場にある「Ticket Office」、「Luncheon」や「WH Smith & Sons」と書かれた昔の標識やメトロポリタン鉄道時代の紋章など、隠された秘宝のように駅のあちこちにちりばめられた、古いものを発見するのもこの駅の楽しみ方といえる。
一方、ベーカー・ストリートといえばこの人、名探偵シャーロック・ホームズ。ベーカールー線のホームや通路ではホームズを象ったデザインのタイル壁画に出会うことができる。また、中央切符売り場にある「Ticket Office」、「Luncheon」や「WH Smith & Sons」と書かれた昔の標識やメトロポリタン鉄道時代の紋章など、隠された秘宝のように駅のあちこちにちりばめられた、古いものを発見するのもこの駅の楽しみ方といえる。 1900年開業だが幾多もの改築、改良工事を経たため、当時の面影はほとんど残されていない。79年にロンドン交通局の依頼で、7年かけて制作、86年に完成したエドゥアルド・パオロッツィによるカラフルなモザイク壁画がこの駅の見どころだ。都会の日常を描いたおよそ1000平方メートルに及ぶ巨大なモザイクアートは、大英博物館のコレクションや映画『ブレード・ランナー』、ジョージ・オーウェルの小説『1984』、ファーストフードなど様々なものに着想を得ているといわれる。またノーザン線ホームにある壁画は、同線の黒色を基調により薄い色調のデザインであるのに対し、セントラル線は同線の赤色を基調にし、鮮やかで明るいものになっている。
1900年開業だが幾多もの改築、改良工事を経たため、当時の面影はほとんど残されていない。79年にロンドン交通局の依頼で、7年かけて制作、86年に完成したエドゥアルド・パオロッツィによるカラフルなモザイク壁画がこの駅の見どころだ。都会の日常を描いたおよそ1000平方メートルに及ぶ巨大なモザイクアートは、大英博物館のコレクションや映画『ブレード・ランナー』、ジョージ・オーウェルの小説『1984』、ファーストフードなど様々なものに着想を得ているといわれる。またノーザン線ホームにある壁画は、同線の黒色を基調により薄い色調のデザインであるのに対し、セントラル線は同線の赤色を基調にし、鮮やかで明るいものになっている。 1906年に建てられた駅でレスリー・グリーンによる設計。グリーンのデザインの特徴といえる赤いテラコッタタイルの外壁を備えた駅舎やホームのタイル模様、草木をかたどった深緑のタイルで飾られたチケット売り場窓口がエレガントで美しい。歴史的建造物として「グレードII」に指定されている。周辺にはサッカーチーム、アーセナルのホームグラウンドがあり、荒くれた労働者階級が集う粗野なイメージのエリアだけに、その中で静かにたたずむ駅の優美な雰囲気とのコントラストが面白い。
1906年に建てられた駅でレスリー・グリーンによる設計。グリーンのデザインの特徴といえる赤いテラコッタタイルの外壁を備えた駅舎やホームのタイル模様、草木をかたどった深緑のタイルで飾られたチケット売り場窓口がエレガントで美しい。歴史的建造物として「グレードII」に指定されている。周辺にはサッカーチーム、アーセナルのホームグラウンドがあり、荒くれた労働者階級が集う粗野なイメージのエリアだけに、その中で静かにたたずむ駅の優美な雰囲気とのコントラストが面白い。 まずはノーザン線ホーム一面に展開される、デヴィッド・ジェントルマンによる木版の原画を転写した壁画アートをじっくりと鑑賞したい。13世紀イングランド国王エドワード1世の妻、エリナー・オブ・カスティルの記念碑が置かれた場所、当時のチャリング村(現在のチャリング・クロス)の様子を100メートルにわたる壁画で表している。
まずはノーザン線ホーム一面に展開される、デヴィッド・ジェントルマンによる木版の原画を転写した壁画アートをじっくりと鑑賞したい。13世紀イングランド国王エドワード1世の妻、エリナー・オブ・カスティルの記念碑が置かれた場所、当時のチャリング村(現在のチャリング・クロス)の様子を100メートルにわたる壁画で表している。 1906年開業当時はレスリー・グリーンの建築だったといわれる駅舎は、29年には改築のために閉鎖され、80年代に取り壊されるに至った。現在目にする、ぐるりと回る大円形状のコンコースはチャールズ・ホールデンの設計によるもの(1928年)。ガンツ・ヒル駅同様、地上には駅舎がない数少ない駅の一つだ。ベーカールー線の茶色、ピカデリー線の濃青色を組み合わせたタイルワークに注目して両方のホームを歩いてほしい。またピカデリー・サーカス広場のシンボル、エロスの像のタイルがどこにあるか探してみるのも楽しい(プラットホームとは限らない点、ご留意を)。
1906年開業当時はレスリー・グリーンの建築だったといわれる駅舎は、29年には改築のために閉鎖され、80年代に取り壊されるに至った。現在目にする、ぐるりと回る大円形状のコンコースはチャールズ・ホールデンの設計によるもの(1928年)。ガンツ・ヒル駅同様、地上には駅舎がない数少ない駅の一つだ。ベーカールー線の茶色、ピカデリー線の濃青色を組み合わせたタイルワークに注目して両方のホームを歩いてほしい。またピカデリー・サーカス広場のシンボル、エロスの像のタイルがどこにあるか探してみるのも楽しい(プラットホームとは限らない点、ご留意を)。 映画監督アルフレッド・ヒッチコックが生まれ育った場所としても知られる、東ロンドンのレイトンストーン。生誕100周年を記念して制作されたヒッチコック作品の有名なシーンをモチーフとしたモザイクアートが、駅舎入口から改札へと向かう通路沿いにずらりと並ぶ(写真は『サイコ』の1場面より)。いくつ分かるか試してみては?
映画監督アルフレッド・ヒッチコックが生まれ育った場所としても知られる、東ロンドンのレイトンストーン。生誕100周年を記念して制作されたヒッチコック作品の有名なシーンをモチーフとしたモザイクアートが、駅舎入口から改札へと向かう通路沿いにずらりと並ぶ(写真は『サイコ』の1場面より)。いくつ分かるか試してみては? 1900年にセントラル・ロンドン鉄道(現在のセントラル線)の駅として、1906年にはベーカー・ストリート・アンド・ウォータールー鉄道の駅が同じ場所に別々に開業。前者はハリー・ベル・メジャーズ、後者はレスリー・グリーンによる設計とデザインが異なる2つの駅舎の外壁が今でも一部残る。 現在は駅のコンコースにあり、もともとはヴィクトリア線のホームにあったのがドイツ人グラフィック・デザイナー、ハンス・ウンガーのタイルアート=写真左。円を意味する「circle」とオックスフォード・サーカスの「circus」をかけあわせ、同駅に乗り入れる3つの路線の色をクロスで表現している。84年からヴィクトリア線には、複雑に路線が入り乱れ、都会のジャングルに迷いこむ人間をパロディ化した「蛇梯子」のタイル=同右=がこれに代わり設置されている。
1900年にセントラル・ロンドン鉄道(現在のセントラル線)の駅として、1906年にはベーカー・ストリート・アンド・ウォータールー鉄道の駅が同じ場所に別々に開業。前者はハリー・ベル・メジャーズ、後者はレスリー・グリーンによる設計とデザインが異なる2つの駅舎の外壁が今でも一部残る。 現在は駅のコンコースにあり、もともとはヴィクトリア線のホームにあったのがドイツ人グラフィック・デザイナー、ハンス・ウンガーのタイルアート=写真左。円を意味する「circle」とオックスフォード・サーカスの「circus」をかけあわせ、同駅に乗り入れる3つの路線の色をクロスで表現している。84年からヴィクトリア線には、複雑に路線が入り乱れ、都会のジャングルに迷いこむ人間をパロディ化した「蛇梯子」のタイル=同右=がこれに代わり設置されている。 1909年創業の高級デパート、セルフリッジズの最寄り駅であり、そのほかの大手デパートや、高級小売店が軒を並べるロンドン随一のショッピング街にあることからか、ジュビリー線のホームのタイルはプレゼントボックスをモチーフとしている。駅の外壁はチャールズ・ホールデンの設計によるものだったが、80年代に取り壊されており、現在はその一部が駅の東側に遺構として痕跡をとどめている。
1909年創業の高級デパート、セルフリッジズの最寄り駅であり、そのほかの大手デパートや、高級小売店が軒を並べるロンドン随一のショッピング街にあることからか、ジュビリー線のホームのタイルはプレゼントボックスをモチーフとしている。駅の外壁はチャールズ・ホールデンの設計によるものだったが、80年代に取り壊されており、現在はその一部が駅の東側に遺構として痕跡をとどめている。 大英博物館の最寄り駅である当駅のホームは、エジプト考古学の発見品やヒエログリフ、古代石版画など大英博物館の所蔵コレクションがモノクロの写真で飾られている。注目してほしいのはギリシャ建築物風の柱の写真。3Dのように浮き出て見える工夫がなされている。
大英博物館の最寄り駅である当駅のホームは、エジプト考古学の発見品やヒエログリフ、古代石版画など大英博物館の所蔵コレクションがモノクロの写真で飾られている。注目してほしいのはギリシャ建築物風の柱の写真。3Dのように浮き出て見える工夫がなされている。 チャールズ・ホールデンによる設計。ホールデンが同時期に設計監督を務めていたロシアのモスクワ地下鉄を参考にした、シンプルながら力強いモダニズム建築のコンコースが特徴的。1930年代に工事が始まったものの、第二次世界大戦中は工事は休止、防空壕として利用されたという。円形交差点の下にあり、地上にまったく駅舎がない点もユニーク。
チャールズ・ホールデンによる設計。ホールデンが同時期に設計監督を務めていたロシアのモスクワ地下鉄を参考にした、シンプルながら力強いモダニズム建築のコンコースが特徴的。1930年代に工事が始まったものの、第二次世界大戦中は工事は休止、防空壕として利用されたという。円形交差点の下にあり、地上にまったく駅舎がない点もユニーク。 ヴィクトリア線のタイルに注目。王様の冠を十字(クロス)にしたモチーフは、キングズ・クロスの駅名の語呂遊びをデザイン化したもの。なお、乗り入れる路線が多い割にはデザイン的に見るものが少ないのが意外。むしろ地上の鉄道駅の方が建築デザインとして一見の価値がある。
ヴィクトリア線のタイルに注目。王様の冠を十字(クロス)にしたモチーフは、キングズ・クロスの駅名の語呂遊びをデザイン化したもの。なお、乗り入れる路線が多い割にはデザイン的に見るものが少ないのが意外。むしろ地上の鉄道駅の方が建築デザインとして一見の価値がある。 ヴィクトリア線のホームを彩るタイルのモチーフ、こちらは駅名そのまま、ヴィクトリア女王の横顔のシルエットがデザインされている。英国人画家エドワード・ボーデンの作品。
ヴィクトリア線のホームを彩るタイルのモチーフ、こちらは駅名そのまま、ヴィクトリア女王の横顔のシルエットがデザインされている。英国人画家エドワード・ボーデンの作品。 ウェストミンスター駅の改札からジュビリー線のホームへと続く空間は、巨大なコンクリートの円柱と梁が十字に組まれ、奥深い地底まで複雑に走るステンレス製の長いエレベーターは映画のセットで登場する宇宙船の内部のような趣だ。建築家マイケル・ホプキンスによる設計で1999年に完成し、2001年には王立英国建築協会(RIBA)賞を受賞。
ウェストミンスター駅の改札からジュビリー線のホームへと続く空間は、巨大なコンクリートの円柱と梁が十字に組まれ、奥深い地底まで複雑に走るステンレス製の長いエレベーターは映画のセットで登場する宇宙船の内部のような趣だ。建築家マイケル・ホプキンスによる設計で1999年に完成し、2001年には王立英国建築協会(RIBA)賞を受賞。 同じく、現代的な建築が印象的なカナリー・ワーフ駅(ジュビリー線)は、広いコンコースに4台並列して走る長いエスカレーターを経て、巨大な半楕円状の窓を仰ぎ見ながら出口へと向かうデザインになっている。そして、窓の外には金融街の高層ビルの姿が映し出される。天井が低く閉塞感を感じる地下鉄駅も多い中、この2駅は広々としており、荘厳かつ近未来的な美を感じさせる。
同じく、現代的な建築が印象的なカナリー・ワーフ駅(ジュビリー線)は、広いコンコースに4台並列して走る長いエスカレーターを経て、巨大な半楕円状の窓を仰ぎ見ながら出口へと向かうデザインになっている。そして、窓の外には金融街の高層ビルの姿が映し出される。天井が低く閉塞感を感じる地下鉄駅も多い中、この2駅は広々としており、荘厳かつ近未来的な美を感じさせる。 メトロポリタン駅の終着駅チェシャムは地下鉄で行けるロンドン市内中心から最も遠い駅である(チャリング・クロス駅から北西に40キロメートル離れている)。1889年開業当初の小さな駅舎=写真左=や信号扱所=同右下、貯水槽=同右上=は歴史的建造物「グレードII」に指定されている。1つしかない地上ホームには緑があふれ、カントリーサイドの長閑な雰囲気が満ちる。ホームにある煉瓦造りの貯水槽は蒸気機関車の水の補給に用いられたもの。また、信号扱所は今年、修復工事が完了した。
メトロポリタン駅の終着駅チェシャムは地下鉄で行けるロンドン市内中心から最も遠い駅である(チャリング・クロス駅から北西に40キロメートル離れている)。1889年開業当初の小さな駅舎=写真左=や信号扱所=同右下、貯水槽=同右上=は歴史的建造物「グレードII」に指定されている。1つしかない地上ホームには緑があふれ、カントリーサイドの長閑な雰囲気が満ちる。ホームにある煉瓦造りの貯水槽は蒸気機関車の水の補給に用いられたもの。また、信号扱所は今年、修復工事が完了した。 ロンドン地下鉄の表示やパンフレット、マップに使われている専用書体「ニュー・ジョンストン」=写真左下=の生みの親が日本人だということをご存知だろうか。目に飛び込んでくるような、くっきりとした書体。この文字は1979年、それまで使われていたジョンストン・フォントを英国在住のグラフィック・デザイナー、河野英一(こうの・えいいち)氏が全面的にリニューアルしたものだ。1916年にエドワード・ジョンストンが生みだした書体は後の書体に多大な影響を及ぼす画期的なものだった。しかし書体は主に駅名表示=同左上=を目的としたため、文字幅が広く、また、ボールド書体(太字)には小文字がないなど、パンフレットや時刻表には不向きだった。1年半かけて制作された河野氏の「ニュー・ジョンストン」書体だが、デザインにおいて同氏が気を使ったのは、意外にも自分のオリジナリティを抑えることだったという。「必要なのは足りない部分を補うこと。人が気づかないように変わっているのが一番いいんです」と、河野氏。イタリック体などを含めて8パターン、1000文字近くが手書きで仕上げられた。「ニュー・ジョンストン」は30年以上、駅名表示から小さなパンフレットに至るまで、愛着をもって使われ続けている。
ロンドン地下鉄の表示やパンフレット、マップに使われている専用書体「ニュー・ジョンストン」=写真左下=の生みの親が日本人だということをご存知だろうか。目に飛び込んでくるような、くっきりとした書体。この文字は1979年、それまで使われていたジョンストン・フォントを英国在住のグラフィック・デザイナー、河野英一(こうの・えいいち)氏が全面的にリニューアルしたものだ。1916年にエドワード・ジョンストンが生みだした書体は後の書体に多大な影響を及ぼす画期的なものだった。しかし書体は主に駅名表示=同左上=を目的としたため、文字幅が広く、また、ボールド書体(太字)には小文字がないなど、パンフレットや時刻表には不向きだった。1年半かけて制作された河野氏の「ニュー・ジョンストン」書体だが、デザインにおいて同氏が気を使ったのは、意外にも自分のオリジナリティを抑えることだったという。「必要なのは足りない部分を補うこと。人が気づかないように変わっているのが一番いいんです」と、河野氏。イタリック体などを含めて8パターン、1000文字近くが手書きで仕上げられた。「ニュー・ジョンストン」は30年以上、駅名表示から小さなパンフレットに至るまで、愛着をもって使われ続けている。 London Transport Museum
London Transport Museum
 近頃、地下鉄駅でこの不思議な迷路のようなものを見かけたことはないだろうか? 一つ一つすべて異なるデザインの「迷路」が、地下鉄全270駅のどこかに展示されている。 2013年、地下鉄開業150周年を記念して、ロンドン交通局はターナー賞の受賞歴もある気鋭のアーティスト、マーク・ワリンガーにアート制作を依頼。各迷路には番号が振られ、その順番は、2009年にギネス・ブック地下鉄最短踏破記録が樹立されたときのルートに基づいているという。ロンドン地下鉄を一つの総体としてとらえ、そこにある長い歴史とデザインを詩的に結び付けた作品となるよう願って制作された。ちなみに「1/270」は、チェシャム駅にある=写真。 次回、地下鉄駅に降り立つ時はこの迷路を探してみては?
近頃、地下鉄駅でこの不思議な迷路のようなものを見かけたことはないだろうか? 一つ一つすべて異なるデザインの「迷路」が、地下鉄全270駅のどこかに展示されている。 2013年、地下鉄開業150周年を記念して、ロンドン交通局はターナー賞の受賞歴もある気鋭のアーティスト、マーク・ワリンガーにアート制作を依頼。各迷路には番号が振られ、その順番は、2009年にギネス・ブック地下鉄最短踏破記録が樹立されたときのルートに基づいているという。ロンドン地下鉄を一つの総体としてとらえ、そこにある長い歴史とデザインを詩的に結び付けた作品となるよう願って制作された。ちなみに「1/270」は、チェシャム駅にある=写真。 次回、地下鉄駅に降り立つ時はこの迷路を探してみては?


 現在はオフィス街となっているシティに位置する、地下鉄モニュメント駅。その駅名は、大火とその後の復興を後世に伝えるために造られた「ロンドン大火記念塔(The Monument)」=写真右=にちなんでつけられている。今は近代的なビルが立ち並ぶエリアとなっており、当時の様子を想像することは難しい。塔の高さは約61メートルで、火元となったファリナーのパン屋からこの塔までの距離と同じになるようにデザインされている。
現在はオフィス街となっているシティに位置する、地下鉄モニュメント駅。その駅名は、大火とその後の復興を後世に伝えるために造られた「ロンドン大火記念塔(The Monument)」=写真右=にちなんでつけられている。今は近代的なビルが立ち並ぶエリアとなっており、当時の様子を想像することは難しい。塔の高さは約61メートルで、火元となったファリナーのパン屋からこの塔までの距離と同じになるようにデザインされている。



 大火の様子を知る資料としては様々な公文書が残されているが、一般市民の行動、通りの様子はどのようなものだったのか。2人の日記作家が自らの体験を綴ったのものが、現在も残されている。
大火の様子を知る資料としては様々な公文書が残されているが、一般市民の行動、通りの様子はどのようなものだったのか。2人の日記作家が自らの体験を綴ったのものが、現在も残されている。 もう1人の日記作家、ジョン・イーヴリン(1620~1706年)=左下絵=は、火薬の製造で財を成した一家に生まれ、オックスフォード大学で学んだ。清教徒革命の時代は戦乱を避けヨーロッパ各地を遊学し、帰国してからはチャールズ2世のお気に入りの知識人の1人として引き立てられた。彼の日記にはピープスのような大胆な記述はないものの、火事の様子を乾燥した空気の状態と結びつけて考察するなど科学者的、全体的視点が感じられる。
もう1人の日記作家、ジョン・イーヴリン(1620~1706年)=左下絵=は、火薬の製造で財を成した一家に生まれ、オックスフォード大学で学んだ。清教徒革命の時代は戦乱を避けヨーロッパ各地を遊学し、帰国してからはチャールズ2世のお気に入りの知識人の1人として引き立てられた。彼の日記にはピープスのような大胆な記述はないものの、火事の様子を乾燥した空気の状態と結びつけて考察するなど科学者的、全体的視点が感じられる。

 今年2月、歴史家のドリアン・ガーホールド氏が、実際に出火元となったパン屋はプディング・レーンのどの位置に建っていたのかを検証した。モニュメントを中心にして半径61メートルの円を描き、様々な当時の地図と照らし合わせ、正確な出火場所を探索。その結果、パン屋が建っていたのは、現在のモニュメント・ストリートの路上であることが判明した。1671~77年にかけて塔が建造されるにあたり、周辺の区画整理が行われたという。当初はなかったモニュメント・ストリートがつくられ、プディング・レーンも西へ移設されたことにより、記録との誤差が生じたと発表した。
今年2月、歴史家のドリアン・ガーホールド氏が、実際に出火元となったパン屋はプディング・レーンのどの位置に建っていたのかを検証した。モニュメントを中心にして半径61メートルの円を描き、様々な当時の地図と照らし合わせ、正確な出火場所を探索。その結果、パン屋が建っていたのは、現在のモニュメント・ストリートの路上であることが判明した。1671~77年にかけて塔が建造されるにあたり、周辺の区画整理が行われたという。当初はなかったモニュメント・ストリートがつくられ、プディング・レーンも西へ移設されたことにより、記録との誤差が生じたと発表した。


 現存するもっとも古い科学学会で、バッキンガム宮殿へと続くザ・マルの近くに拠点を置く「ロイヤル・ソサエティ」=写真=は、正式名称を「The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge(自然についての知識を深めるためのロンドン王立協会)」という。これはレンをはじめ、物理学者のロバート・フックや数学者のジョン・ウォリスなど、自然哲学および実験哲学に興味を持つオックスフォード大の学者たちがお互いの家や大学を行き来し、それぞれの専門知識やアイディアを交換しては議論をたたかわせ、切磋琢磨していた集まりが原形となっている。
現存するもっとも古い科学学会で、バッキンガム宮殿へと続くザ・マルの近くに拠点を置く「ロイヤル・ソサエティ」=写真=は、正式名称を「The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge(自然についての知識を深めるためのロンドン王立協会)」という。これはレンをはじめ、物理学者のロバート・フックや数学者のジョン・ウォリスなど、自然哲学および実験哲学に興味を持つオックスフォード大の学者たちがお互いの家や大学を行き来し、それぞれの専門知識やアイディアを交換しては議論をたたかわせ、切磋琢磨していた集まりが原形となっている。

 万有引力の法則を発見した天才科学者アイザック・ニュートン=右絵(1643~1727)。他人をおおっぴらに賞賛することはほとんどなかったという彼だが、万有引力の法則と運動方程式について述べた著作『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』の中で、レンを「もっとも優れた数学者の1人」と記している。
万有引力の法則を発見した天才科学者アイザック・ニュートン=右絵(1643~1727)。他人をおおっぴらに賞賛することはほとんどなかったという彼だが、万有引力の法則と運動方程式について述べた著作『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』の中で、レンを「もっとも優れた数学者の1人」と記している。














 同社のウェブサイトで紹介されているレシピ通り、ソフトなWhite Farmhouse Breadに、マチュア・チェダー・チーズ、Branston Original Pickleを挟んだサンドイッチを作って試食。濃厚でホロホロとした熟成チーズとピクルスの酸味、程よい歯応えが、フワフワのホワイト・ブレッドに包まれ、絶妙なコンビネーションを見せる!
同社のウェブサイトで紹介されているレシピ通り、ソフトなWhite Farmhouse Breadに、マチュア・チェダー・チーズ、Branston Original Pickleを挟んだサンドイッチを作って試食。濃厚でホロホロとした熟成チーズとピクルスの酸味、程よい歯応えが、フワフワのホワイト・ブレッドに包まれ、絶妙なコンビネーションを見せる!









 酢、マスタード、ターメリック、ショウガなどの香辛料で作った漬け汁に、カリフラワー、玉ネギ、キュウリなどの野菜を漬け込んだ色濃い黄色のピカリリは、ベイクト・ポテトなどジャガイモと一緒に食べるのが好まれている。また、コールドミートのサンドイッチやホットドッグにも合う。
酢、マスタード、ターメリック、ショウガなどの香辛料で作った漬け汁に、カリフラワー、玉ネギ、キュウリなどの野菜を漬け込んだ色濃い黄色のピカリリは、ベイクト・ポテトなどジャガイモと一緒に食べるのが好まれている。また、コールドミートのサンドイッチやホットドッグにも合う。

 【材料(3~4人分)】
【材料(3~4人分)】 ピクルスを食べた残りの漬け汁に、固ゆでにした卵を2時間漬ければ、こんなにかわいい色に変身!浅漬けなら漬け汁の味がほんのりと移る程度で食べやすい。ホーム・パーティーの1品にいかが?
ピクルスを食べた残りの漬け汁に、固ゆでにした卵を2時間漬ければ、こんなにかわいい色に変身!浅漬けなら漬け汁の味がほんのりと移る程度で食べやすい。ホーム・パーティーの1品にいかが?



